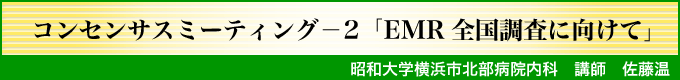早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)については、現在は施設ごとの報告に終始し、全国的なデータの集計は行なわれていない。そのため、適応基準についてのガイドラインの遵守、評価可能な臨床試験としての適応拡大の実施の実態、合併症の頻度と対策、再EMRや開腹手術の判断基準、進行癌再発の可能性、長期予後の観察、癌死の頻度、等々、その実態は明らかにされず、未解決のままにされている。また、昨今報道される内視鏡事故によって社会的関心も高まっている。
こうした状況を背景に、日本胃癌学会では、EMRの全国調査を計画しており、今学会ではその全国調査に向けて、会員より意見を聞くためのコンセンサスミーティングが持たれた。各演者からEMRの現状と今後の課題についてそれぞれ講演があり、討論が行なわれた。
講演のタイトルは、「内視鏡的粘膜切除術の課題とその克服」とされ、Strip biopsy、切開剥離法(ESD)のそれぞれのデータベースの構築について、治験への対応など、各演者よりレポートがあり、最後には総合討論も短時間ながら行なわれた。
最初の演者(国立がんセンター中央病院 齊藤大三)からは、「委員会設置の背景」として、現状の分析が行なわれた。
1985年、消化器内視鏡学会における「胃生検に関するシンポジウム」の中で初めてEMRが取り上げられて以来、年を追うごとにEMRは普及が進み、各種学会誌を調べたところ、1998年から2000年の三年間に、国内79施設で11106症例に施行されているという。しかし、こうした普及にもかかわらず、技術の統一や合併症に対して議論する場は存在していなかった。一方デバイスの開発も急速に進んでおり、「ITナイフ」や「Flexナイフ」など、メーカーと医師が共同で開発したデバイスがそれぞれ別個に存在している実態となっている。
その為、有志ある医師たちによって技術の水準を議論するために設けられた研究会も、現状では独立に四つ存在するようになった。
こうした背景下に設置された全国調査委員会は、
・胃EMRの実態を把握し、ガイドラインの見直しの客観的資料を提供する。
・胃EMRの適応拡大に伴う規約改正の要否を明らかにする。また、必要に応じて用語を含め、具体案を提示する。
・普及著しいEMR患者数を無視できず、EMRを含む全国登録を実施することを目的に掲げ、また 具体的な調査項目としては、
・適応基準について、胃癌ガイドラインの遵守の程度、適応拡大が評価可能な状況にあるか。
・手技・処置具の整理については、多岐にわたる切除方法の分類が可能か、保険医療の想定範囲と倫理的・経済的課題の対応。
・合併症について、予想外、あるいは予想される合併症の頻度、その治療技術別の評価の可能性。
・局所再発の実態とその取り扱いでは、再EMRと開腹手術の判断基準、進行癌再発の頻度。
・長期予後の実態について、十分な予後観察が行なわれているか、癌死の頻度はどのくらいか。
などである。実際にはまず積極的にEMRを行なっている全国13施設において、2001年1月より12月までの実態をレトロスペクティブに調査し、それによって全国規模で解析が必要な事項を明らかにし、本格的なプロスペクティブな全国調査を2005年をめどに考えているという。
次に、「Strip biopsyのデータベース」(埼玉県立がんセンター消化器内科 多田正弘)では、演者の1983年8月から2002年12月までの20年間の経験を基に、その調査結果が報告された。
診断については、最近5年間では、内視鏡的にM癌と判定した病変の468例中446例で、病理的にもM癌とされ、95.3%の診断率であり、SM癌だった症例でも外科手術を必要とした例はなかった。効果判定では、同じく最近5年間で446例中89例の5mm以下の例でも、3例はECとなっており、全体でもEAが65%、EBが13%、ECが22%であった。また隆起型の方が陥凹型よりEAの可能性が高かったとのことだった。
偶発症の経験は、3711施行回数に対して、術中出血33例、術後出血28例で、そのうち外科手術となったものは1例、また穿孔は1例だった。遺残病変の発生は、最近5年間でEAでは0/290、EBで11/58、ECで29/98、2cm以下の病変では440病変中11病変、2cm以上の病変では142病変中29病変で、外科手術が必要となったのは、2cm以上の3例のみだったという。
治療時間は、内視鏡挿入から抜去まででいずれも10分以内であり、実際の治療時間はほんの数分の範囲だった。
生存に関しては、遺残例でも非遺残例でも、いずれにも胃癌死はなく、差はなかった。
以上のような結果から、strip biopsyは一定頻度で遺残再発が見られるが、追加の内視鏡的治療で根治可能であるなど、治療時間が短く、偶発症は極めて少ない治療法だ結論付けられる。
「切開剥離法のデータベース(1)」(国立がんセンター中央病院内視鏡部 後藤田卓志)では、演者の施設での切開剥離法(Endoscopic
Submucosal Dissection:ESD)の現状と、そのデータベースについて報告された。
まずはじめに、切開剥離法(ESD)は、診療報酬の点で他の治療法と比べた際にかなりの赤字となり、矛盾点があることが、リンパ節郭清を伴わない腹腔鏡下胃切除術や大腸ポリテクトミー等と比較して指摘され、全国調査後に診療報酬の改訂も提案すべきだとコメントされた。
この施設では、ガイドライン上の適応である2cm以下の潰瘍のない分化型M癌以外に、2cm以上の潰瘍のない分化型M癌、潰瘍を伴う3cm以下の分化型M癌、そしてSM癌の3cm以下の症例に適応拡大して施行している。
1987年から2002年までの1441病変について、ガイドライン内の治療と診断されて施行した1036例では、評価対象切除例950例中非治癒切除は139例(15%)で、その内100例ほどは本来外科手術適応と考えられる深さの浸潤の進んだ病変だった。すなわちガイドライン内病変と判断した病変でも、10%程度は結果的に適応外のものが含まれていたことになる。
局所再発について、一括切除の場合には治癒切除が82%、非治癒切除が14%で、切除後の病理評価ができなかった例は4%にすぎないが、分割切除の場合には治癒切除は45%、非治癒切除が24%、そして病理評価不能例が31%にのぼる。
分割切除に関しては、この施設での適応拡大への取り組みも、一括切除が可能になって初めてなされているなど、分割切除については慎重に取り扱う必要があり、全国調査での予後調査の必要性が強調された。
2000年以降では、ガイドライン内と判断された症例782例(一括切除率95%)において、EAが75%、EBは21%、ECが4%で、腫瘍の遺残は10例のみだった。EAの内、病理の評価でガイドライン内(2cm以下M分化型癌)だったのはその89%で、11%が結果的にガイドライン外だった。またEB例でもその31%にSM癌、リンパ節転移、脈管侵襲が認められ、EC例とあわせて非治癒切除が84例となり、外科手術の施行、肝転移があるなどの結果であり、規約による根治度の評価に改良すべき点のあることが指摘された。
また、ファイルメーカーを用いたデータベースについても紹介された。
今後の課題としては、EMR後のリンパ節再発や遠隔転移の検証をすべきであるとのこと。全国調査では、診療報酬の新設、一括切除の必要性、根治度評価の再検討の必要性、早期胃癌におけるESDの妥当性の検討などが、課題として挙げられた。 |