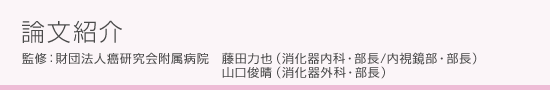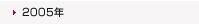Dukes'BおよびCの大腸癌患者の予後因子としての遺伝子腫瘍マーカー
Chieu B. Diep, et al., J Clin Oncol 21(5), 2003:820-829
10年間経過観察された初発大腸癌患者220例を対象として、遺伝子変化と臨床病理学的所見との関連を検討した。
腫瘍からDNAを採取し、これまで大腸癌で変異が報告されている染色体1p, 14q, 17p, 18q, 20q上の12の座の対立遺伝子不均衡を分析するとともに、マイクロサテライト不安定性(MSI)を判定した。また、TP53変異の臨床的重要性についても再評価した。
その結果、17pまたは18qが欠失した腫瘍を有する患者は、これらの変化のない腫瘍を有する患者よりも生存期間が有意に短く(p=0.021およびp=0.008)、Dukes'Bに限っても有意であった(p=0.025およびp=0.010)。さらに、17pと18qの両方が欠失した例では、どちらか一方が欠失した例よりも予後不良であった。20qにおけるコピー数変化をみると、3倍までの軽度増加例では、無変化例や3倍以上の高度増加例よりも生存期間が有意に長く(p=0.009およびp=0.030)、Dukes'Cの例に限ると顕著であった。また、MSI陽性例では生存期間が長い傾向にあった(p=0.071)。TP53のL3亜鉛結合ドメインにかかわる変異は、本研究のコホートでも生存期間と有意に相関することが確認され、Dukes'Bに限った検討でも同様の結果を得た。このように遺伝子変化と病理学的所見の間にはいくつかの関連が認められた。
本研究により17p, 18q, 20qの遺伝子変化とTP53の状態はDukes'BおよびCの進行度を細分類するための付加情報となり、治療法選択に寄与すると考えられた。
臨床応用が期待される、遺伝子学変化による予後判断
Dukes分類に代表される、深達度, リンパ節転移, 遠隔転移に基づく進行度分類は大腸癌の予後因子として最も重要であり、術後補助化学療法の適応も現時点では進行度分類によって決定されている。しかしながら、同一の進行度であっても予後良好な例と不良な例があることは事実であり、組織学的進行度のうえに追加できる予後因子を臨床家は求めてきた。
本研究で検討された遺伝子の変化も臨床応用が期待されているもので、17p, 18qの欠失はDukes'Bにおける予後不良因子であり、20qのコピー数の増加が軽度(3倍以下)であることはDukes'Cにおける予後良好因子であった。今後、遺伝子変化を日常臨床における治療方針決定に用いるためには、さらに多数の遺伝子変化と予後の関連をマイクロアレイ解析などにより明らかにする一方、簡便かつ迅速な分析法が必要と考えられる。
(消化器外科・大矢雅敏)