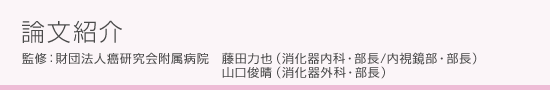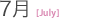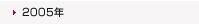大腸癌肝転移に対する肝切除を伴った/あるいは伴わない凍結治療と肝動注療法 −腫瘍数はいくつまでが治療の限度?
Dong Bo Yan, et al., Cancer 98(2), 2003:320-330
肝転移に対し肝切除やアブレーションをする場合、腫瘍数はいくつまでが妥当なのか結論は出ていない。
この研究では大腸癌の肝転移に対する治療法として、肝切除の有無にかかわらず開腹下に凍結治療をし、その後に肝動注療法を行った患者のデータを後ろ向きに解析した。治療前の検査として、骨シンチ、肺CT、腹部血管造影下CTを行ったが、PETは施行していない。
対象患者を2002年6月まで、または死亡日までフォローアップし、Kaplan-Meier法とCox比例ハザードモデルを用いて17の予後因子を検討した。
172例の患者を対象とし、治療の内訳は、92例は凍結治療のみ、80例は凍結治療と肝切除を行った。凍結治療後157人に肝動注療法を施行した。凍結治療後30日以内に1例が心筋梗塞で死亡し、治療全体に伴う合併症は27.9%にみられた。生存期間中央値は28カ月であり、良好な予後との相関を示した独立因子として、患者年齢50歳以下、原発巣が高分化あるいは中分化腺癌、凍結治療した腫瘍径が3.5cm未満、凍結治療時における肝外病変の完全治療、療法前CEAの低値、が認められた。単変量解析では、療法施行時に未治療の肝外病変がない、療法後CEAの正常化、CEAレベルの著明な低下、が良好な予後と統計学的に有意に相関した。腫瘍数は予後と相関しなかった。根治治療できた146例の1, 2, 3, 4, 5年生存率はそれぞれ89, 65, 41, 24, 19%であった。腫瘍数別にみた生存期間中央値は、1, 2, 3, 4, 5, 6〜7, 8〜12個でそれぞれ、32, 29, 30, 31, 27, 37, 21カ月であった。腫瘍数が6〜7個あった25例の5年生存率は、25%であった。
大腸癌の肝転移をすべて治療できれば、転移個数は予後を規定する因子にはならない。
肝病変の根治が予後を大きく左右する
大腸癌の肝転移は予後を左右する大きな因子である。この論文は肝病変が根治できれば、肝転移の個数は予後因子とならないという点で、肝臓外科医、インターベンション専門医を勇気付けるものである。肝腫瘍に対するアブレーションとしての凍結治療はわが国では普及していないが、肝予備能を悪化させずに3.5cm以下の腫瘍なら根治できるとされ、さらに大きな腫瘍は肝切除を併用することで腫瘍をすべて取り除くことが可能になる。しかし、肝病変がコントロールできても、最終的には肺などの肝外病変が予後を左右することになり、再発様式を考慮したうえで、抗癌剤、分子標的薬剤(将来的)などを用いた術後化学療法を行うことが大切である。また、術後動注療法の有用性に関しても、動注療法と全身化学療法との無作為化比較試験を通じて検討するのが望ましい。
(内科・猪狩功遺)