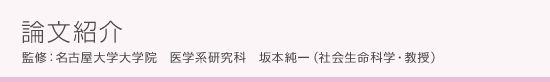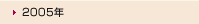UGT1A7 とUGT1A9 の遺伝子多型は結腸・直腸癌患者における
capecitabine+irinotecan併用療法の奏効率と毒性の予測因子となりうる
Carlini LE, et al., Clin Cancer Res. 2005; 11(3): 1226-1236
Capecitabineとirinotecanは転移性結腸・直腸癌の治療に広く使用されている。この2剤の併用療法の奏効率や毒性に、薬物標的酵素(thymidylate synthase:TS)あるいは代謝酵素(UDP-glucuronosyltransferase:UGT)の遺伝子多型が影響するとの仮説を検証した。
組織学的に確認された転移性結腸・直腸癌患者で、年齢18歳以上、Karnofsky performance status(KPS)≧70%の患者67例を対象として、irinotecan(100または125mg/m2をday
1とday 8に静脈内投与)とcapecitabine(900または1,000mg/m2をday
2からday 15まで1日2回経口投与)による治療を、3週間を1サイクルとして施行した。末梢血からgenomic DNAを抽出し、Pyrosequencing、GeneScan、直接塩基配列決定法を用いてUGTの多型(UGT1A1、UGT1A6、UGT1A7
およびUGT1A9 )およびTSの多型を解析した。
全対象患者における奏効率は45%であった。21例(31%)はグレード3〜4の下痢を発現し、3例(4.5%)は開始から2サイクルの間にグレード3〜4の白血球減少を呈した。酵素活性が低いUGT1A7
遺伝子型であるUGT1A7 *2/ *2
(6例)およびUGT1A7 *3/ *3
(7例)は、良好な抗腫瘍効果(p=0.013)および重度の消化管毒性の低発現(p=0.003)と有意に相関し、UGT1A9−118(dT)9/9
遺伝子型は毒性軽減(p=0.002)および抗腫瘍効果の増強(p=0.047)と有意に相関した。UGT1A1、UGT1A6、およびTSの遺伝子型は、毒性や抗腫瘍効果と相関しなかった。
これらの結果は、UGT1A7 多型あるいはUGT1A9 多型は、結腸・直腸癌患者におけるcapecitabine+irinotecan併用療法の抗腫瘍効果および毒性の予測因子となりうることを強く示唆している。特に低活性型のUGT1A7
多型あるいはUGT1A9(dT)9/9 多型を有する患者では、抗腫瘍効果が高く毒性は低いと考えられる。
UGT1A7 とUGT1A9 の遺伝子多型は
irinotecanの奏効率と毒性の予測因子となりうるか?
この論文ではirinotecan+capecitabine併用療法の毒性と有効性がUGT1A 遺伝子型と関連があるか否かについて論じられ、過去のirinotecan毒性の報告とは相反する結果が報告されている。一般にUGT1A1
の変異型(*28/ *28
)では、irinotecanの活性型SN-38が肝臓でSN-38Gへと不活性化されにくく血中濃度が上昇するため好中球減少をきたすとされるが、本研究ではUGT1A1
遺伝子型と毒性に関連なしとしている。これは本研究ではirinotecan投与レジメンの違いにより、好中球減少がほとんど発現しておらず主な毒性が下痢であったためと考えられる。下痢に関して筆者らはUGT1A
の酵素活性が高いと血中のSN-38が速やかにSN-38Gとして胆汁から腸管内へと移行し、腸管内細菌により再びSN-38へと活性化されて消化管毒性をもたらすと推論している。しかしながら、UGT1A7
は主に上部消化管に発現するため胆汁排泄に対するインパクトは肝臓に発現するUGT1A1 よりも低いはずである。また、UGT1A1 *28/ *28
はGilbert症候群(軽症の遺伝性黄疸)の原因遺伝子であると同時にirinotecanの毒性発現危険遺伝子型であるが、本研究では軽度の高ビリルビン血症患者ならびにGilbert症候群患者を除外している。さらにcapecitabineにも消化管毒性が認められるが、この点については全く触れられていない。
以上のように、この報告がirinotecanの毒性・効果と遺伝子多型との関連性を十分に論じているとは言い難いが、irinotecan+capecitabine併用療法における下痢発現という観点からは新しい知見を提供しているものということができる。
監訳・コメント:山口大学医学部 硲 彰一(消化器・腫瘍外科学[第2外科]・講師)