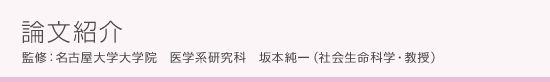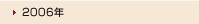Imatinib脱落後の進行GIST患者におけるsunitinibの抗腫瘍効果および安全性に関する無作為化比較試験
Demetri GD, et al., Lancet 2006; 368(9544): 1329-1338
消化管間質腫瘍(GIST)の発生機構は大部分がK I T 遺伝子あるいはPDGFRA遺伝子の機能獲得型の変異といわれている。キナーゼドメイン活性阻害薬であるimatinibは、進行切除不能GISTに対して臨床的予後改善のある唯一の有効な薬剤である。ところが、これまでの研究で、初期耐性が5%に生じ、また二次耐性が約2年の中間値で生じることが知られてきている。そして、このimatinibへの耐性獲得後のsecond lineについては、有効な治療法が確立されていないのが現状である。
一方、sunitinibもimatinibと同様に複数の受容体チロシンキナーゼのATP結合部位を競合的に阻害することで活性を抑える経口薬であるが、imatinibとは異なる特性を有すると推測され、imatinib耐性症例に対する治療薬として期待されている。
本試験は進行GISTに対してimatinib治療後の耐性症例、あるいは忍容不能症例を対象として、sunitinibの抗腫瘍効果および忍容性の評価を目的として施行された無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同第III相試験である。
手術放射線等の治療に適応せず最初にimatinib治療を施行され、耐性もしくは副作用にて継続不能な症例を対象とし、imatinib治療中止後2週間以上経過した後に、2:1の比でsunitinib群とプラセボ群に無作為に割り付けした。Sunitinib 50mg/日あるいはプラセボを1日1回の経口投与で4週間投与、2週間休薬した(1サイクル6週間)。主要評価項目は無増悪期間(TTP)とした。Intention-to treat解析、改変intention-to treat解析、per-protocol解析を施行した。本試験はClinicalTrials.govのNCT00075218番に登録された。
2003年12月から2005年1月にわたって11ヵ国の56施設より登録された312症例が参加した。Sunitinb群(207例)とプラセボ群(105例)には治療前の状態に差は認めなかった。試験は、最初の149例の腫瘍進行または死亡に対する中間解析でプラセボ群に比較してsunitinib 群のTTPでの優越性が得られたため(2005年1月)、その後は非盲検で施行した。TTPの中央値はsunitinib群で27.3週間(95%CI 16.0〜32.1)、プラセボ群で6.4週間(95%CI 4.4〜10.0)であった(ハザード比 0.33、p<0.0001)。また、sunitinibの有意性は、年齢、性別、体重、人種、痛みの症状、PS、最初に診断されてからの期間、イマチニブの治療期間、病変部位に関係なく認められた。また、OSについても同様に、sunitinib群においての延長が認められた。忍容性は良好であり、共通して発現した治療関連有害事象で最も多かったのは倦怠感、下痢、皮膚変色、悪心であった。
Imatinib脱落あるいは治療継続不能の進行GIST患者において、sunitinibはプラセボと比較して病態コントロール、優れた生存関連の評価項目を含め治療効果が有意に優れていることが示された。また、忍容性においても容認できることが示された。
分子標的治療薬sunitinibの可能性
本論文は、進行消化管間質腫瘍(gastrointestinal stromal tumor:GIST)のimatinib耐性あるいは治療継続不能例に対するセカンドラインとしてのsunitinibの可能性について検討したものである。分子標的治療薬であるimatinibは、2001年にGISTに対する効果が報告されて以来、進行再発GISTに対するファーストラインの治療薬として確立され、高い臨床効果を示している。一方、その耐性の出現が問題となってきている。一次耐性では、K I T 遺伝子変異の有無や部位との関連が認められ、また二次耐性症例の多くでは新たなK I T 遺伝子の変異獲得が認められており、KITタンパク質の構造の違いがその原因であると考えられている。
本研究における対象の多くはimatinibに対する耐性例と考えられる症例であり、その群に対して高い治療効果を得たという興味深い結果であった。Sunitinibは、imatinibと異なるメカニズムによりチロシンキナーゼ受容体を阻害することから、KITタンパク質の構造の違いにより効果が異なると考えられる。さらに、腫瘍におけるK I T 遺伝子変異とその効果を研究することで、より詳しい分子標的治療のメカニズムの解明を図り、セカンドライン治療としてテーラーメイドな治療を行うことができる可能性も示唆された。
監訳・コメント: 大阪大学大学院医学系研究科 高橋 剛(外科学講座消化器外科)