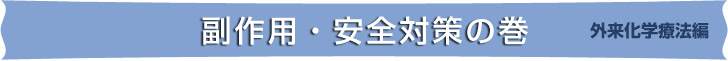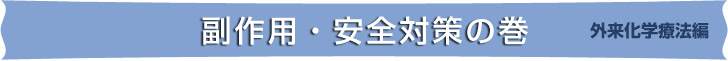佐藤(昭和大)
佐藤(昭和大) 次に、患者教育に話題を移しましょう。副作用の第一の発見者は患者さん自身であり、そのためには患者教育が重要です。服薬指導は薬剤師の大切な役割の1つだと思いますが、野村先生はどの段階で患者さんと接しておられますか。
野村(杏林大・薬) 初回投与時の指導と2回目の投与時の評価です。加えて、レジメンごとに副作用が起こりやすい時期がありますので、そのたびに事前にお伝えしています。初回指導は点滴前に行いますが、2回目の評価やコースの合間の指導は点滴中に行います。外来化学療法では、患者さん自身が副作用に気づくことが大切ですので、事前に情報提供をしておくのです。
佐藤 患者説明用の資材はどうされていますか。
室(愛知がん) 看護師と薬剤師が中心になって、副作用対策に関する患者向けの冊子をつくりました。プロトコールごとにつくっているものもあります。
篠崎(県立広島) 製薬会社提供の資材は1つの薬剤に特化しているものが多いため、オリジナルの資材と組み合わせて使用しています。FOLFOX、FOLFIRIについては、国立がんセンター中央病院のものを参考にして院内で作成しました。
野村 製薬会社が提供している患者向け資材は、治療スケジュールに支持療法薬などが含まれていないので、外来化学療法室の薬剤師がレジメンごとにオリジナルのものを作成しています
(図3)。また、すべての薬剤について、副作用の説明書を患者さんに渡して、「薬との因果関係があるかどうかは薬剤師が判断するので、何でも言ってください」とお話ししています。
瀧内(大阪医大) レジメン登録数は少なくとも100以上はありそうですが、全部つくられるのですか。
野村 私がつくるのは外来化学療法室で行うレジメンだけですが、それでもやはり大変な作業です。しかし、患者さんに「あなたが受けるのは珍しい治療法だから、説明用資材はありません」というのは気の毒だと思います。
理想としては、米国国立癌研究所(NCI)のようなwebサイトで共通の資材がダウンロードできるようになることです。当院でも、近いうちに腫瘍内科のホームページから説明資材をダウンロードできるようにして、近隣の医療機関や調剤薬局の方に見ていただきたいと思います。
 瀧内
瀧内 地域医療を展開していく上でも、副作用の説明がばらばらだと困るので、共通の資材があったほうがいいと思いますね。
佐藤 こうしたオリジナルの資材の問題点はありますか。
野村 個人がつくることによって、バイアスがかかることです。副作用は第III相試験から引用していますが、資材に載せる副作用と載せない副作用があって、何%で切るのかは、作成者である私個人の判断になります。例えば、自分の基準で味覚障害を載せなかったが、実際に味覚障害を起こした患者さんが出たとき、その責任はどうすべきか。この話は、東京都病院薬剤師会のがん領域専門薬剤師研究会でも話題になったのですが、難しいところです。
篠崎 せっかく手渡しても、高齢の方などでは、なかなか興味を示さない場合もありますね。「渡したから安心」というわけにはいかないところに、ジレンマを感じることがあります。
佐藤 患者日誌も有用だと思いますが、使っておられますか。
金井(聖路加・看) 一部の科ではお渡ししていますが、毎日詳細に書き込まれる方と、ほとんど書かない方がおり、個人差が大きいですね。FOLFOXを行っている患者さんには、薬剤の減り具合などのチェック項目を記載した「在宅化学療法日誌」
(図4)をお渡ししています。
図3 患者さん向け cetuximab+CPT-11療法説明資材(杏林大学医学部付属病院、一部抜粋)
[拡大表示]
 ※web掲載用に資材の一部を改変しています。また、資材中の薬剤費は個々の患者さんに合わせて計算しています。
図4 在宅化学療法日誌(聖路加国際病院)[拡大表示]
※web掲載用に資材の一部を改変しています。また、資材中の薬剤費は個々の患者さんに合わせて計算しています。
図4 在宅化学療法日誌(聖路加国際病院)[拡大表示]