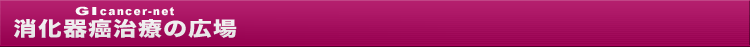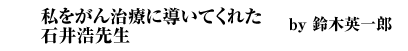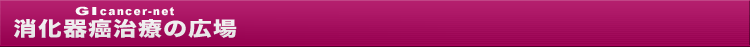肝胆膵(腫瘍)内科を標榜しています。 肝胆膵(腫瘍)内科を標榜しています。
この診療科名は私の知るところ、国立がんセンター中央病院と東病院の2ヵ所しかない※のではないかと思います。
本邦では大学における臓器別講座制の影響から、肝胆膵のがんは消化器内科・外科が担当することが多いと思います。しかし、内科は診断、治療は外科という分業で、総合的に診る仕掛けがありません。
米国仕込みの臨床腫瘍学は、臓器別の縦割り診療から治療別横断的診療の一大主要分野といえます。有名雑誌に掲載される膵がん臨床試験の著者が、実は肺がんや乳がんの専門家であることはよくあることです。私の知るところ、米国に肝胆膵がん専門の化学療法医はほとんどいません。肝胆膵領域がんは病態が複雑で、しかも化学療法の効果が不確実です。局所療法適応の判断、閉塞性黄疸の処置など、チーム医療が浸透している欧米の施設なら肝胆膵特有の病態に不慣れな化学療法医でも安心して肝胆膵領域がんを担当できますが、日本では当分難しいと思います。
肝胆膵がんは稀少疾患でなく、むしろ患者数からみれば主要疾患です。それにもかかわらず「臨床腫瘍学の秘境」なのかもしれません。でも、これでよいわけはありません。
まだまだ臨床腫瘍学本格の一派ではありませんが、私たちは肝胆膵領域がんの専門家であることをアピールします。そして、私たちのプライマリ・エンドポイントは世界をリードする中核グループとなることです。肝胆膵領域がんの化学療法はまだまだ未開発な部分が多く、本邦と欧米との差はほとんどありません。欧米に比べて患者数が多い本邦に必要なのは、良質の臨床試験を迅速に遂行する能力のある共同研究グループの確立です。そして、その萌芽はJCOG消化器がん内科グループ内に育ちつつあります。
※:P.S. あとで調べたところ、いくつかの施設の標榜科名に肝胆膵内科があるようです。しかし、肝胆膵領域がんの臨床腫瘍学を専門にやっている内科は少なくとも10年前までは私たちだけだったと思います。いつの間にか仲間が増えているのですね。
|