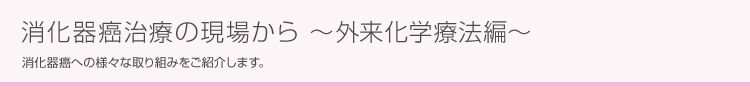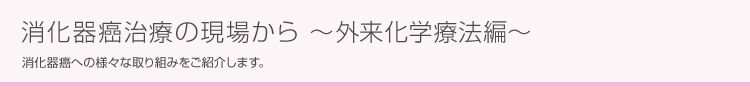Q. アメニティールームというのは外来化学療法室として少々変わった名称ですが、その由来は。
| |
 |
A: 「化学療法」あるいは「癌」という文字が入っている名称は患者さんへの響きが悪く、利用される方も入りづらいことを考慮し、患者さんを「もてなす」という意味で、この名前にしました。
患者さんからも、他の患者さんに自分の病気を知られにくいという点で、ご好評をいただいています。
|
Q. 患者さんが来院し、アメニティールームで点滴を受けるまでの流れを教えていただけますか。
A:当日、採血やレントゲンのある方は診察の前に検査を済ませていただきます。血液・化学検査の場合、40分から1時間で結果が出ます。所定の時間になったら、患者さんは主治医の診察室に行き、主治医から化学療法実施の決定が出た時点で、アメニティールームに電話連絡があります。
本来は治療決定の電話があった時点で薬剤師に調剤を依頼したいのですが、アメニティールームの看護師としては再度患者さんの状態を確認しておきたいので、患者さんがアメニティールームの受付をし、特に異常がないことを確認した後に調剤を依頼します。
ベッド予約に関しては、診察時間に合わせて予約を取っていますので、待ち時間はなく治療に入れます。
終了後はバイタル観察等で問題がなければ、そのまま帰宅していただきます。
|
 |
|
図. 外来化学療法の流れ

Q. がん化学療法看護認定看護師の資格を取るのはかなり大変だと聞いていますが、病院側からのサポートはあるのですか。
A: 当院では化学療法に限らず、認定看護師の育成に重点を置いており、本人が希望し、十分に意欲があると認められれば、「出張扱い」つまり基本給が支給された状態で研修を受けることができます。がん化学療法看護認定看護師の場合、研修期間は半年です。
Q. 看護師さんの新人研修では、がん化学療法教育プログラムというのがあるそうですが、具体的にはどのようなものですか。
A: 今年から始まったのですが、卒業後1年目の看護師を対象として、まず「患者さんを守る」ということを徹底して教育した上で化学療法の基礎的なことを段階的に勉強していきます。
「癌とは何か」「CVポートの管理」など毎回テーマを決めて、月1回1時間、1年間で6、7回の勉強会を開催しています。
化学療法に関してはがん化学療法看護認定看護師2名が講師を担当し、完全に自由参加としています。
Q. 専任の薬剤師さんは、調剤以外に服薬指導等もされるのですか。
A: 病棟では服薬指導を行っていますが、アメニティールームではまだできていないのが現状です。
今後は副作用等について患者さんに説明するとか、抗癌剤専門の薬剤師(がん専門薬剤師)認定制度ができたので、できれば資格を取っていくようにしたいと思います。
Q. 外来化学療法におけるチーム医療の重要性について、お話しいただけますか。
A: 化学療法では患者さんが中心にいて、その周りに主治医、臨床腫瘍科医、看護師、薬剤師、栄養士、さらに医療スタッフと患者さんをつなぐメディカルコーディネーターなどの職種が関わっています。
全体をコーディネートするのは医師ですが、各部門のスタッフが専門性を最大限に発揮し、同じ方向、同じベクトルに向かって進むことが大切です。
Q. メディカルコーディネーターとはどのような職務なのでしょうか。
A: ひと言で言うと、医療スタッフと患者をつなぐ“架け橋”のような存在です。日常臨床の中で医師、看護師では説明できないような、例えば化学療法の費用、セカンドオピニオンなど幅広く患者さんに説明します。さらに患者さんの不安等のニーズを引き出して、医療スタッフにフィードバックする役目もあります。もともと、看護師や医療事務を行っていたスタッフで、外来の受付前のメディカルコーディネーター室に4名が常時待機しています。
Q. 化学療法に関して、地域医療連携はどのようになっていますか。
A: 当院は2年前に北陸地方で初めて地域医療支援病院に認定されました。連携室を設置し、積極的に取り組んできたため、紹介率・逆紹介率共に高くなってきています。例えば連携病院のうち、外来で抗癌剤治療をしている施設には、できるだけ患者さんを逆紹介して、FOLFOXでのCVポートの抜針や、補液管理などをお願いしています。また、地域の医師と勉強会を開催しています。
Q. 予約がない場合は治療を受け付けていないのですか。
A: 基本的にはお断りしたいのですが、患者さんの状態もありますので、ベッドの余裕があれば、お受けしています。予約が一杯の場合は1日ずらしていただけないか、主治医の先生と相談します。