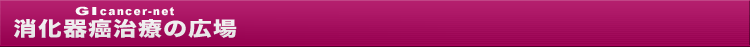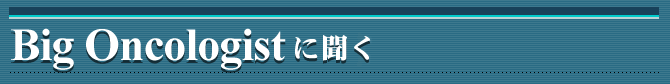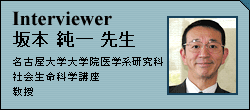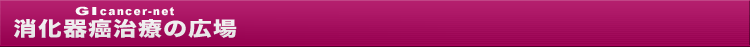|
胃癌切除後の補助化学療法と INT-0116 |
|
 |
|
| 本日は、主に米国における上部消化管癌と大腸癌の治療についてお話を伺いたいと思います。最初に、胃癌のIntergroup trial 0116(INT-0116)についてご紹介ください。 |
 Macdonald(以下細字):Intergroup
trialは、胃癌切除後の補助化学療法を全米で検討することを目的にスタートしました。1960〜1980年代にかけて、補助化学療法を評価する臨床試験がいくつか行われましたが、胃癌切除後の補助化学療法にはまったくベネフィットが認められませんでした。一方、胃癌切除後あるいは再発患者に対する放射線療法は、再発率を減少させ、時には顕微鏡レベルの再発でさえ完全に消失させることがわかっていました。そこで我々は、胃癌切除後の患者を手術単独群と術後chemoradiation
群に無作為割り付けして比較する試験デザインが合理的だと考えました。INT-0116は1990年代初頭に行われたので、化学療法としては当時利用可能であった治療薬のなかから
LV/5-FUが多く使われました。 Macdonald(以下細字):Intergroup
trialは、胃癌切除後の補助化学療法を全米で検討することを目的にスタートしました。1960〜1980年代にかけて、補助化学療法を評価する臨床試験がいくつか行われましたが、胃癌切除後の補助化学療法にはまったくベネフィットが認められませんでした。一方、胃癌切除後あるいは再発患者に対する放射線療法は、再発率を減少させ、時には顕微鏡レベルの再発でさえ完全に消失させることがわかっていました。そこで我々は、胃癌切除後の患者を手術単独群と術後chemoradiation
群に無作為割り付けして比較する試験デザインが合理的だと考えました。INT-0116は1990年代初頭に行われたので、化学療法としては当時利用可能であった治療薬のなかから
LV/5-FUが多く使われました。
登録症例数は603例、各群に約280例ずつの症例が無作為割り付けされ、chemoradiation 群にはLV/5-FUを放射線照射(45Gy/25回)の前に 1サイクル、照射中に 2サイクル、照射後に 2サイクル投与しました。その結果、手術単独群と比べてchemoradiation 群では再発率が有意に減少し、5年生存率も有意に改善しました(42% vs. 23%)。この試験に組み入れられた患者は予後不良症例が多く、85%がリンパ節転移を有し、65%がT3でした。Chemoradiationは、こうした stage III 以上の患者において明らかなベネフィットがあり、さらにサブセット解析では、リンパ節転移のない15%の患者においてもベネフィットが認められました。 |
| 逆に chemoradiationの効果があまり期待できないのは、どのような患者ですか。 |
未分化癌ではそれほどベネフィットが得られないかもしれません。日本と米国では、外科手術への取り組みがだいぶ異なります。米国の外科医はD2郭清をあまり行わず、実施率は10%程度にすぎません。INT-0116でD2郭清を受けた患者は600例中55例程度で、54%はD0郭清ですから、多くの患者がリンパ節切除を受けていなかったわけです。この状況は、D2郭清が標準治療となっている日本やヨーロッパとはまったく異なっています。D2郭清を受けた患者では、chemoradiationによるベネフィットが若干認められましたが、各群25例ずつという少数なので、統計学的検出力が低く、確かなことはいえません。
現在、米国で術後chemoradiationは標準治療となっていますが、他の国でも標準治療となるかどうかは、日本や韓国、ヨーロッパ諸国の外科医による臨床試験の結果次第だと思います。 |
| 私は、放射線科医ではないのでわからないのですが、臨床試験を実施するにあたって、放射線療法のquality control はどのようにされたのでしょうか。 |
よい質問ですね。この試験を行うにあたって、それが我々の懸念の 1つでした。そこで我々は、無作為割り付けされた患者が 1ヵ月間のLV/5-FU治療を受けている間に、担当する放射線科医に放射線治療計画を立てさせ、すべての放射線治療計画を Kansas City の放射線腫瘍医である Dr. Smalleyに検証してもらいました。その結果、3分の 1の治療計画は誤っており、3分の 2は重要な照射部位が見逃されていました。つまり under treatmentであったり、重要なリンパ節が見落とされていたり、腎臓、肝臓、心臓などへの照射が多すぎる危険なものだったのです。残念なことに、1990年代初頭の米国の放射線医はこの種の放射線治療に熟練していなかったといえるでしょう。
術後chemoradiationは正しく行わなければ患者へのダメージが大きい治療だということをよく理解し、経験豊かな放射線腫瘍医が行わなければなりません。そこで、ASTRO(American Society for Therapeutic Radiology and Oncology)では、適切な放射線治療を行うためのコースやウェブサイトを設けました。治療に適した患者の選択や安全な実施に関するトレーニングにより、現在、chemoradiationは米国で広く行われています。対象となる患者は胃切除から54日以内で、試験開始前日までに経口、あるいは経胃瘻チューブまたは経空腸瘻チューブで1日1,500Kcal 以上を摂取できていなければなりません。重篤な肝・腎・心疾患などを有する高齢者は除外します。ですから、かなり低リスクの患者に術後chemoradiationを行っているわけです。 |
 |
chemoradiation の新 regimen、ECFについて |
|
 |
|
| 先生は、chemoradiationの新しい regimenを評価する臨床試験を新たに始められましたね。 |
| Epirubicin/CDDP/5-FUの併用療法(ECF)の効果を検討する Intergroup trial を始めました。これは、英国・Royal Marsden Hospital のDavid Cunningham 先生らのグループが開発した regimenで、ECFを放射線療法の前後に実施する群を、対照群(INT-0116試験の治療群)と比較する試験です。症例の集まりが遅いのですが、米国の医師は食道癌でも胃癌でも、ただちに手術を行わず、術前に補助化学療法を行いたがることが原因だと思います。この試験でも約600例の登録を予定しているのですが、まだ150例程度しか集まっていません。もうしばらく時間がかかると思います。 |
 |
日本の臨床試験の質と問題点 |
|
 |
|
| 日本の胃癌治療と臨床試験について、どのような印象をお持ちですか。米国の試験の結果は、日本人にも適用できると思われますか。 |
 臨床試験の質や、医師の能力は素晴らしいと思います。日本の先生方は術後の補助化学療法に興味を持たれていますね。特にTS-1への関心が高く、確かに有効だということが日本での経験でわかっていますが、米国ではまだ認可されていません。 臨床試験の質や、医師の能力は素晴らしいと思います。日本の先生方は術後の補助化学療法に興味を持たれていますね。特にTS-1への関心が高く、確かに有効だということが日本での経験でわかっていますが、米国ではまだ認可されていません。
Chemoradiationによって日本人患者の予後が改善するかどうかにかかわらず、臨床試験を行わずして何も言うことはできません。他の部位、例えば直腸癌において、直腸間膜の完全切除は通常の直腸切除より再発率が低く、こうした患者に対する放射線療法は再発率を低下させることがわかっています。これは、優れた手術と放射線療法の併用で局所制御率が改善することの一例です。同じD2郭清を行っても、放射線療法を行うか行わないかでベネフィットは違ってくると思うのですが、試験が終了するまではわかりません。 |
| 日本の臨床試験の問題は、症例がなかなか集まらないということです。5年間で 200〜250例程度しか集められないのです。米国では、なぜ短期間に 500例もの症例を集めることが可能だったのですか。 |
症例登録は1998年に終了したので、7年間にこれだけの症例を集めたことになります。米国で消化器癌治療にかかわっている共同研究グループを同じ臨床試験に参加させたのです。これが Intergroup trial です。他に類似の臨床試験がありませんでしたし、試験に参加した医師は胃癌切除後に行うべき標準的な補助化学療法はないと考えていたので、自分の患者を最良の標準治療である手術単独群に割り付けることを望んでいました。そのため、試験の終盤には月に10人程度の症例が集まっていました。すごい数ですが、医師自身がそのほうがよいという自信を持っていたから、患者を試験に参加させたのです。
我々が今抱えている問題は、術前の補助化学療法の重要性が認識された一方で、術後補助化学療法の臨床試験に対する関心が低いということです。それで、症例の集まりが遅いのです。どんな臨床試験でも、統計学的検出力を得るに十分な数の症例を組み入れなければ結果の解釈ができません。その試験から何の知見も得られないとすれば、多くの労力と時間を無駄にしたことになり、参加していただいた患者さんに対しても恥ずべきことではないでしょうか。 |