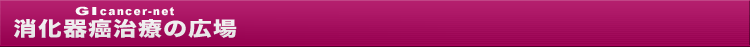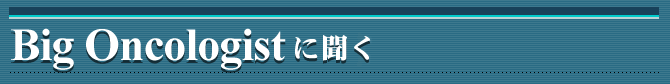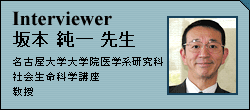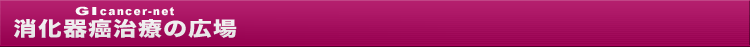|
メタアナリシスについて |
|
 |
|
| この臨床試験を含めたいくつかのメタアナリシスについてのお考えを聞かせてください。 |
メタアナリシスは有用です。胃癌の補助化学療法に関しては、少なくとも 4つの大きなメタアナリシスが公表されており、補助化学療法群にベネフィットがみられる傾向があります。一般に、メタアナリシスから傾向がわかるとプロスペクティブな臨床試験による検証が計画されます。ただし、メタアナリシスに基づいて治療を決定することは決してありません。
米国では、現在のところ補助化学療法として適切な regimenがあると自信を持っていえません。恐らく、将来的には血管内皮細胞増殖因子(VEGF)の阻害など分子標的治療を含めたものが候補として挙げられるでしょうが、現時点ではchemoradiationが標準的治療であると考えています。 |
 |
結腸癌治療の現状 |
|
 |
|
| 次に、結腸癌についてお伺いしたいと思います。日本では oxaliplatin(L-OHP)が正式に認可されました。米国でも MOSAIC試験の後に、FDAが術後補助化学療法として L-OHPを承認したと聞いています。米国でのL-OHPの使用状況はいかがですか。 |
 L-OHPは広く使われるようになりました。進行癌の
first line治療の 1つであるFOLFOX regimenで主に使われています。MOSAICの結果に基づいて、FOLFOX
4はリンパ節転移陽性のstage III 結腸癌に対する術後補助化学療法の標準 regimenと考えられています。 L-OHPは広く使われるようになりました。進行癌の
first line治療の 1つであるFOLFOX regimenで主に使われています。MOSAICの結果に基づいて、FOLFOX
4はリンパ節転移陽性のstage III 結腸癌に対する術後補助化学療法の標準 regimenと考えられています。
一方、stage II の患者にはそれほど有効でないということで、stage IIにはあまり使われていません。大規模臨床試験やメタアナリシスをみても、進行癌では生存率が15〜20%改善しているのに対し、stage II では4〜5%の改善しか得られていません。
米国では最近、VEGFを標的としたモノクローナル抗体のbevacizumab と cetuximabが進行結腸癌治療薬として承認されました。Bevacizumabは、進行結腸癌に対する 5-FUとの併用療法が承認されたので、FOLFOXあるいはFOLFIRIとの併用で、広く first line治療に使われています。多くの医師が最初に FOLFOXかFOLFIRI regimenで治療を開始し、それで進行した場合に他のregimenに変えるか、あるいは最初に FOLFIRI でスタートして進行した場合にFOLFOXに変えるべきだと考えています。それも奏効しない患者には、irinotecan(CPT-11)と抗上皮増殖因子レセプター(EGFR)モノクロナール抗体 cetuximabの併用が候補となります。Cetuximabは、特にCPT-11 ベースの化学療法に奏効しなかった患者に適応があり、有効性が認められています。
2005年1月にオーランドで行われた 2005 Gastrointestinal Cancers Symposiumにおいて、preliminaryですが興味深い報告がありました。CPT-11/cetuximab か CPT-11/cetuximab+bevacizumabのいずれかの治療を受けた進行結腸癌患者を比較したところ、bevacizumabを追加した群では奏効率が2倍高かったということで、3剤併用がより有効であることを示唆するデータだと思います。
進行結腸癌領域では、Intergroup trial の 1つが始まったところです。“dealer’s choice trial”と呼ばれるもので、医師は最初のregimenとしてFOLFIRI と FOLFOXのいずれかを選択でき、その後に無作為化してcetuximab併用群または bevacizumab 併用群、あるいはcetuximab+bevacizumab 併用群に割り付けます。この 3つの治療を比較することができるので、とても興味深い試験になると思います。 |
 |
Bevacizumab の有効性を検討するC-08試験 |
|
 |
|
| C-08試験について教えてください。 |
| C-08は、結腸癌患者を対象としてNSABP(National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project)が実施している、術後補助化学療法の first lineとしての bevacizumab の有効性を検討するための試験で、LV/5-FU/L-OHP投与(mFOLFOX 6 regimen)が基本regimenとなり、それにプラセボを併用する群と bevacizumabを併用する群に無作為割り付けします。約1年前に始まり、非常に速く患者が集まっています。Bevacizumabの抗血管新生作用によって、転移癌細胞に栄養を供給している血管を閉塞させて転移を抑制することが期待され、非常に興味深い試験になると思います。 |
| NSABPからは何例の症例が集まったのですか。 |
| 約2,500例、各群1,200例程度が集まりました。術後補助化学療法の試験としてはよく集まったと思います。 |
| 対象患者はstage III ですか。 |
| stage II と III です。NSABP は常に stage II 患者を対象に含めています。米国の他の Intergroup trial でも stage II の患者が含まれていますが、腸閉塞や穿孔のあるようなリスクの高いstage II 患者です。 |
| それは NSABPグループとは少し違っているのですね。 |
 はい。Stage
II 患者に対する術後補助化学療法から得られるベネフィットは4〜5%にすぎず、米国の多くの腫瘍専門医は術後化学療法を望みません。特に今日では、進行結腸癌であっても治療は可能で、例えば、小さな肝転移があっても治療で腫瘍が縮小すれば
6ヵ月後には肝の転移巣を切除できることがわかっています。しかしNSABPでは、stage II 患者も対象に含めています。 はい。Stage
II 患者に対する術後補助化学療法から得られるベネフィットは4〜5%にすぎず、米国の多くの腫瘍専門医は術後化学療法を望みません。特に今日では、進行結腸癌であっても治療は可能で、例えば、小さな肝転移があっても治療で腫瘍が縮小すれば
6ヵ月後には肝の転移巣を切除できることがわかっています。しかしNSABPでは、stage II 患者も対象に含めています。
また、腫瘍の分子パラメータを検査して化学療法が必要な患者とそうでない患者を選ぼうとしているのですが、こちらは標準的治療としての準備がまだできていません。特に興味深い分子パラメータは、DCC遺伝子がある第18番染色体の長腕の欠失です。この部位に欠失がなければ、stage II での切除後の再発率は5〜7%以下です。
|
| 非常に低いですね。そのような患者には術後化学療法は必要ないわけですね。 |
はい。その他にマイクロサテライト不安定性(MSI)が重要です。MSI を有する散発性結腸癌患者の15%は、phenotype と genotypeも不安定です。これらの患者は、手術をしたほうが生存率が高まる傾向があり、5-FUベースの術後補助化学療法が奏効するように思えません。それを検討する試験が進められていますが、恐らくCPT-11やL-OHP、その他の薬のほうが有効だと思います。
治療が奏効したstage II 患者のDCCとMSI を解析する試験がECOG(Eastern Cooperative Oncology Group)で始まっています。Stage II 患者をFOLFOX群と経過観察群に無作為割り付けしていますが、分子パラメータをprospectiveに用いて患者を選択した初めての試験ですから、どれくらいうまくいくかはわかりません。
私が結腸癌の研究を始めてもう 30年になりますが、最初の22〜23年間は5-FU だけが唯一使用可能な薬剤だったので、持続静注や高用量あるいは低用量のLVとの併用など、あらゆる投与方法を試みました。しかし現在、我々はCPT-11、L-OHP、cetuximab、bevacizumab を手にし、多彩な治療戦略をとることができます。また、腫瘍専門の外科医と親密に連携をとり、転移性疾患に対して積極的なアプローチができるわけです。我々は患者を選択して転移病変を外科的に切除することに強い関心をもっています。もし、肺や肝臓、腹腔内に転移のある患者に 6ヵ月ほど化学療法を行い、新しい転移がみつからないなら、外科的切除は大いに患者の助けになります。 |