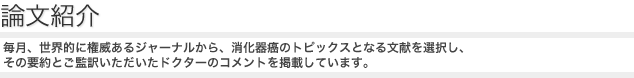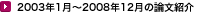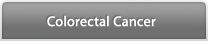監修:東海中央病院 坂本純一(病院長)
下部食道の局所進行腺癌患者に対するDocetaxel+Cisplatin+Panitumumab+放射線療法による術前補助療法後手術の第II相試験(ACOSOG Z4051)
Lockhart AC., et al. Ann Oncol., 2014 ; 25(5) : 1039-1044
局所進行食道癌については、CROSS試験がCarboplatin(CBDCA)+Paclitaxel(PTX)毎週投与を用いた術前放射線化学療法による術後成績の改善が報告されて以来、術前放射線化学療法が標準療法として確立している。一方で、腺癌では扁平上皮癌ほどの成果があがっていないという問題も残されている。食道癌では頻繁にEGFR過剰発現がみられ、生存成績低下につながっていることから、ACOSOG Z4051試験では切除可能な食道腺癌患者を対象として、術前放射線化学療法にEGFR標的療法を追加して評価した。本試験はCROSS試験の結果が発表される前に計画されており、化学療法として選択された薬剤はDocetaxel(DOC)+Cisplatin(CDDP)であるが、この2剤併用は転移食道癌に対する放射線療法との組み合わせにおいて奏効率、生存期間が優れ、忍容性もあるとする複数の試験結果に基づいた。PanitumumabはEGFR結合能の高さ、安全性から選択した。
対象は18歳以上、ECOG/Zubrod PS0-1、生検で確認された下部食道または食道胃接合部の切除可能腺癌(Siewert I/II型)、臨床ステージ(AJCC第6版)T3N0M0またはT2/3N1M0またはT2-3N0/1M1aの未治療の患者などとした。
適格患者にはPanitumumab 6mg/kg(1時間で静注)+DOC 40mg/m2(1時間で静注)+CDDP 40mg/m2(1〜2時間で静注)投与、およびCDDP投与前後に生理食塩水500mLを投与した。化学療法は2週ごとのday 1に、5コース実施した。放射線療法は5週目から開始し、1.8Gy28分割で5〜6週にわたり外部照射を行った(総線量50.4Gy)。放射線化学療法終了後4〜6週にCTまたはPET-CTにて効果を評価し、転移が認められなかった患者に治癒的切除術を実施した。
なお、本治療法の評価は今回が初めてのため、患者募集は最初の6例が登録された時点で一時中断し、治療後12週の有害事象を評価した。2回の投与調整および/または治療中止を要する副作用が2例以上にみられた場合は試験を中止し、治療プランを立て直す計画であった。
主要評価項目は術後のpCR(病理学的完全寛解)率である。従来の完全寛解率20%に15%以上の上乗せ効果(目標寛解率35%以上)を90%の検出力、片側検定P<0.10で検出するために、必要症例数は63例と設定された。
2009年1月〜2011年7月に24施設から70例が登録され、適格患者は65例であった。年齢中央値は61.0歳、男性90.8%、Siewert I型55.4%、M1a 13.8%、N1 80.0%、T3 89.2%であった。
化学療法投与はDOCで80%、CDDPで76%、Panitumumabで73%の患者が予定通り完了した。放射線療法は92%の患者がプロトコル完了または最小限受容できる調整で完了した。手術は54例で実施された。手術が実施されなかった主な理由は、病勢進行(4例)、患者の拒否(4例)、主治医の決定(3例)などであった。
54例のうち33.3%(95%CI 22.8-43.9%)がpCRに達し、near pCR率は20.4%(95%CI 11.4-29.4%)で得られた。中央値26.3カ月の追跡期間中、65例中32例(49%)が死亡した。OS中央値は19.4ヵ月、3年OSは38.6%、2年DFSは41.4%であった。
安全性の評価は70例で行った。血液学的副作用はgrade 3が24.3%、grade 4が30.0%に、また非血液学的副作用はgrade 3が47.1%、grade 4が31.4%に認められた。grade 3/4の副作用としては、リンパ球減少(42.9%)、白血球減少(37.1%)、貧血(17.1%)、好中球減少(17.1%)、食道炎(18.6%)、脱水症状(18.6%)、悪心(15.7%)が高頻度に発現した。抗EGFR療法に特有の皮疹は94.3%でみられたが、grade 3/4は5.7%であった。この皮疹の頻度・重度と良好な治療成績の間に関連は認められなかった。
術後のICU入室日数は平均5.6±5.8日で、平均入院日数は15.8±21.3日であった。手術により2例(3.7%)が死亡した。
下部食道の局所進行腺癌患者に対するDOC+CDDP+Panitumumabを用いた術前放射線化学療法は、pCR+near pCR率が53.7%であった。これは患者の95.5%がN1またはM1aであったことを考えると有望な数字である。pCRは33.3%で目標の35%に届かなかったが、pCRとnear pCRで生存率に有意差がないという報告もあるので、本研究の今後の追跡で良好なPFSが得られる可能性もある。しかし、本レジメンは副作用が強く、安全性について問題があり、毒性の低い他のレジメンでも本試験に近いpCRが得られることを考慮すれば、今後本レジメンをさらに推進する根拠は乏しい。さらに本試験のほか、ECOG 2205試験やREAL 3試験の結果も合わせて考慮すると、食道・胃癌のすべての患者に対してモノクローナル抗体による抗EGFR療法を施行することは良い治療戦略とはいえないだろう。
日本発の標準治療の確立に期待
米国で行われた切除可能な下部食道および食道胃接合部の腺癌に対するPanitumumabを併用した術前化学放射線療法(CRT)の検討である。約半数がpCRまたはnear pCRであったが、毒性が強いので今後さらに検討されるべきレジメンではないというのが著者の結論である。
切除可能食道癌の治療は、欧米では術前CRTが標準治療とされているが、わが国では食道癌(扁平上皮癌)に対する標準治療は放射線を用いない術前化学療法である。CROSS試験は手術単独に対して術前CRTの有効性を示した第III相試験であるが、術前化学療法に放射線治療を付加することの有用性を明確に示したエビデンスはない。また欧米の食道癌の臨床試験は、対象症例に下部食道の腺癌が多く、しかも扁平上皮癌とも同時に評価されていることが多いので、これらの結果を直ちにわが国に適応するのは難しい。その点本試験は、対象患者を切除可能な下部食道および食道胃接合部の腺癌に限定し、主要評価項目もpCR率としているのでわかりやすい。しかし、わが国の手術では、従来から局所制御を重視したリンパ節郭清が積極的に行われているので、局所制御を目的とした術前放射線治療の意義は少ない可能性があり、特に接合部腺癌に対する術前放射線治療にはあまり馴染みがないのが現状であろう。本試験では根治照射に匹敵する高めの線量(50.4gy)が照射され33.3%のpCRを得ているが、CRTの有害事象も多く、重篤な術後合併症も、死亡率3.7%、再挿管率22.2%と低いとは言えない。また、pCR症例に手術が必要なのかという議論もある。
わが国では食道腺癌、接合部癌の頻度が低く、接合部癌は食道外科と胃外科で手術術式を含めて治療方法が異なることもあり、標準治療は確立していない。今後、わが国でも症例が増加することが予測され、胃癌で欧米にくらべて良好な治療成績を誇るわが国発の標準治療の確立が望まれる。
監訳・コメント:帝京大学医学部付属病院 上部消化管外科 福島 亮治(教授)
GI cancer-net
消化器癌治療の広場