
 佐藤
佐藤 それでは、2nd-lineには何を使われますか。
高橋 1st-line はL-OHPベース + Bevacizumabを使いますので、2nd-lineではベースレジメンをFOLFIRIに替え、Bevacizumabはそのまま続けます。
KRAS 野生型の患者さんでも、すぐに抗EGFR抗体に切り替えることはしていませんが、将来的に切除可能となることも見据えて、2nd-lineでFOLFIRI + 抗EGFR抗体を選ぶ場合もあります。2nd-lineと3rd-lineは、患者さんの好みや転移の状態によっても違ってきますので、院内ですべて統一しているわけではありません。
辻 2nd-lineでは1st-lineで使用していないレジメンを用いますので、1st-lineがFOLFOXだった場合はFOLFIRIです。2nd-lineでは基本的にBevacizumabは併用せず、
KRAS 野生型であれば抗EGFR抗体の併用を考慮します。
吉野 当院の2nd-lineは、
KRAS 野生型の場合はFOLFIRI + Panitumumab、
KRAS 変異型ではFOLFIRI単独です。
加藤 1st-line、2nd-line、3rd-lineと3つのラインがありますが、分子標的治療薬は抗VEGF抗体と抗EGFR抗体の2種類しかありませんので、この2剤をどのラインに組み入れるかということになります。NCCN、大腸癌治療ガイドライン
(図3) のいずれも、
KRAS 野生型の3rd-lineで推奨されている分子標的治療薬は抗EGFR抗体だけですので、抗EGFR抗体は3rd-lineで使いたい。そう考えると、2nd-lineはBevacizumabを使うか、使わないかという選択になります。
1st-lineでL-OHPベースを使用した場合、2nd-lineはFOLFIRI になりますが、単独ではパワー不足に感じられるため、Bevacizumabを併用しているのが現状です。ただし、患者さんの状態が悪く、3rd-lineを施行できる可能性が低い場合には、2nd-lineで抗EGFR抗体を併用することもあります。
佐藤 2nd-lineでベースレジメンを変えるのは全員共通でしたが、分子標的治療薬の使い方はそれぞれに違うようですね。高橋先生と加藤先生は引き続きBevacizumabを使い、辻先生と吉野先生は化学療法 + 抗EGFR抗体、または化学療法単独ということでした。
2nd-lineのL-OHP/CPT-11ベースレジメンと分子標的治療薬併用のエビデンスとしては、
E3200試験 (FOLFOX ± Bevacizumab)
7) がありますが、新たにFOLFIRI ± Panitumumabの有用性を比較・検討した
20050181試験が報告されました
8)。吉野先生もこの試験に参加されたそうですが、簡単にご紹介いただけますか。
吉野 20050181試験は、5-FU系抗癌剤不応の切除不能大腸癌患者を対象に、
KRAS statusを前向きに測定し、2nd-lineとしてのFOLFIRI ± Panitumumabの有効性を検証した第III相試験です。本邦で初めて参画した切除不能大腸癌の国際共同試験です
8)。PFS (progression-free survival: 無病生存期間) はPanitumumab併用群で2ヵ月の有意な延長が示され (p=0.004)、OSにおいては有意差はなかったものの(p=0.12)、2ヵ月の延長が認められました。また、奏効率はPanitumumab併用群で35%、FOLFIRI単独群では10%と、2nd-lineとしては非常に高い奏効が得られています (p<0.001)。
当院では本試験の結果を踏まえ、
KRAS 野生型に対する2nd-lineとして、FOLFIRI + Panitumumabを施行しています。
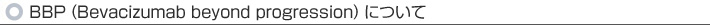
 佐藤
佐藤 2nd-lineにおけるFOLFIRI + Panitumumabの有用性が示された一方で、大規模観察研究 (
BRiTE) で提唱されたBBP (Bevacizumab beyond progression) の考え方
9) に基づき、Bevacizumabを1st-line、2nd-lineと継続して使う先生もいらっしゃいました。
BRiTEは、化学療法歴のない患者を対象に、化学療法 + Bevacizumabの有用性と安全性を検証したコホート研究です。BBPに関しては、前向き試験の結果が出ておらず、ガイドラインでも推奨されていない状況ですが、どのようにお考えですか。
加藤 BRiTEでは、1st-lineのPD後もBevacizumabを継続投与した群 (BBP群: 642例) のOSが31.8ヵ月であり、非BBP群 (531例) の19.9ヵ月と比べて有意な延長が示されたので、この結果をある程度信用してもよいと考えています。もちろん、前向き試験の結果を待つ必要があるとは思いますが、「
KRAS 野生型症例の2nd-lineを細胞毒性抗癌剤単独にする」「3rd-lineの有効なレジメンを失う」という選択肢しかないのも困ります。ですから、今のところは2nd-lineでもBevacizumabを継続使用するという戦略をとっています。
佐藤 今のお話は
KRAS 野生型の場合ですね。現在、ガイドラインで3rd-lineが提示されているのは
KRAS 野生型のみで、
KRAS 変異型に対して推奨されるレジメンはありません。今後、
KRAS 変異型に対する新たな治療の開発が待たれます。



