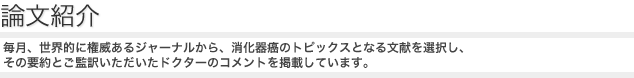5月
国立がん研究センター中央病院 消化管内科/頭頸部・食道内科 科長 加藤 健
大腸癌
KRASG12C変異陽性大腸癌に対するAdagrasib単剤療法とAdagrasib+Cetuximab併用療法
Rona Yaeger, et al.: N Engl J Med. 388(1): 44-54, 2023
KRAS遺伝子変異のなかでも、コドン12の変異であるKRASG12C変異は大腸癌患者の3~4%に生じると報告されている1-3)。KRAS変異陽性転移再発大腸癌においては、3次治療以降では治療の有効性が限定的であり、新規治療薬の開発が切望されていた。KRASG12C変異は他のKRAS変異よりも生存期間が悪いことが報告されており4)、このKRAS変異に対する薬はundruggableと考えられてきていた。しかしKRASのswitch IIポケットに対して結合し、変異しているシステインと共有結合することでGTP結合を阻害できる低分子が開発され、期待されている。
AdagrasibはKRASG12C変異蛋白に対する経口小分子阻害薬であり、変異蛋白に不可逆的かつ選択的に結合し不活性化させる作用をもつ5,6)。Adagrasibは既報において、治療歴のあるKRASG12C変異陽性の大腸癌やその他複数の癌種の患者で効果が示されている5)。大腸癌においてはKRASG12C阻害薬の使用で上皮成長因子受容体(EGFR)を介した適応的フィードバックによりRAS-MAPKシグナル伝達経路の再活性化が起こる可能性があり、KRASG12C阻害薬と抗EGFR抗体薬の併用でEGFRの再活性化が抑制され、より効果的である可能性が示唆されている7)。
本論文では、現在進行中のKRYSTAL-1試験(第I/II相試験)において、既治療のKRASG12C変異陽性転移性大腸癌に対するAdagrasib単剤療法およびAdagrasibと抗EGFR抗体薬であるCetuximabの併用療法の有用性が検証されている。
本試験は第I/II相非盲検非無作為化臨床試験である。
主な適格基準は、18歳以上、ECOG PS 0-1で標準治療が終了しているKRASG12C変異陽性の切除不能進行もしくは転移性大腸癌患者であった。Adagrasib単剤療法を行う群ではRECIST v1.1で測定可能病変を有することが適格基準とされたが、AdagrasibとCetuximabの併用療法群では必須ではなかった。
除外基準としては、活動性の脳転移や癌性髄膜炎の患者、投与開始の2週間以内に全身化学療法や放射線治療を行っている患者などであった。
Adagrasib単剤療法を行う群ではAdagrasib 600mgを1日2回経口投与し、AdagrasibとCetuximabの併用療法を行う群では単剤療法と同量のAdagrasibに加えて、Cetuximabの毎週投与(初回量400mg/m2、その後は250mg/m2)または2週ごと(500mg/m2)の投与を行った。
本試験ではRECIST v1.1での病勢進行を認めた場合でも、研究者の判断で同治療を継続することが許容された。また、Adagrasib単剤投与群では13週以上病勢制御が得られている場合に、Cetuximabとの併用療法へのクロスオーバーが認められた。
Adagrasib単剤療法群では、主要評価項目は奏効割合(完全奏効または部分奏効)であり、副次評価項目は奏効期間、無増悪生存期間、全生存期間、1年生存率、安全性であった。AdagrasibとCetuximabの併用療法群では主要評価項目は用量制限毒性を含めた安全性であり、副次評価項目は奏効割合であった。
上記検討に加え、治療前と2、4コース目開始時に血漿検体を採取し、それぞれの治療法においてcirculating tumor DNA(ctDNA)でのKRASG12C変異のクリアランスが評価された。また、事後分析としてTP53もしくはPIK3CA変異のバイオマーカーをベースラインで評価し、単剤療法または併用療法での腫瘍の反応との関連性が調べられた。
単剤療法コホートでは閾値奏効割合が10%、期待奏効割合が30%と設定され、95%信頼区間が作成された。Adagrasib単剤療法は治療効果が評価可能な40例のうち、7例以上で奏効を認めた場合に有効であると考えられた。AdagrasibとCetuximabの併用療法では、投与された最初の7例の患者の中で用量制限毒性を認めた患者数が十分少ない場合に有望であるとされた。単剤および併用療法のいずれでもKaplan-Meier法を用いて奏効期間、無増悪生存期間、全生存期間、1年生存率が評価された。
2022年6月16日の時点で、44例がAdagrasib単剤療法を受け32例がAdagrasibとCetuximabの併用療法を受けていた。追跡期間の中央値はそれぞれ20.1ヵ月と17.5ヵ月であり、治療期間の中央値はそれぞれ5.9ヵ月と7.3ヵ月であった。年齢中央値はそれぞれ59歳(29~79歳)、60歳(41~74歳)であり、女性の割合はそれぞれ50%と53%であった。2群間で患者背景は類似しており、すべての患者で前治療としてフッ化ピリミジン系薬剤が使用され、前治療のレジメン数の中央値は3であった。
単剤療法群では、奏効割合は19%(95% CI: 8-33)であった。奏効期間中央値は4.3ヵ月(95% CI: 2.3-8.3)、無増悪生存期間中央値は5.6ヵ月(95% CI: 4.1-8.3)、全生存期間中央値は19.8ヵ月(95% CI: 12.5-23.0)であった。併用療法群では、奏効割合は46%(95% CI: 28-66)であった。奏効期間中央値は7.6ヵ月(95% CI: 5.7-未到達)、無増悪生存期間中央値は6.9ヵ月(95% CI: 5.4-8.1)、全生存期間中央値は13.4ヵ月(95% CI: 9.5-20.1)であった。
ctDNAの反応については、2コース目時点で単剤療法群の55%、併用療法群の88%でKRASG12C変異アレルの95%以上の消失を認めた。さらに、いずれの治療群でも奏効割合とTP53変異またはPIK3CA変異の有無との関連性は認められなかった。
Adagrasib単剤療法群およびAdagrasibとCetuximabの併用療法群における治療関連有害事象の頻度は全gradeでそれぞれ93%、100%であった。20%以上の頻度で認めた有害事象は単剤療法群で下痢(66%)、嘔気(57%)、嘔吐(45%)、倦怠感(45%)であり、併用療法群では嘔気(62%)、下痢(56%)、嘔吐(53%)、ざ瘡様皮疹(47%)、倦怠感(47%)、乾皮症(41%)、頭痛(31%)、めまい(25%)、斑点状丘疹(25%)、口内炎(22%)であった。Grade 3または4の治療関連有害事象の発現率はそれぞれの群で34%、16%であった。減量を要した治療関連有害事象は単剤療法群で39%、併用療法群で31%の患者で観察された。併用療法群では16%の患者でCetuximabの継続が困難な有害事象が生じたが、すべての患者でAdagrasib単剤での治療継続が可能であった。どちらの治療群でもgrade 5の有害事象は観察されなかった。
本試験で報告されたAdagrasib単剤療法の有効性は、同じくKRASG12C阻害薬であるSotorasibと同等かむしろ良好な結果を示していた。またBRAFV600E変異陽性大腸癌に対するEncorafenibとCetuximabの併用療法の報告と同様に分子標的薬の有効性を示しており8)、現在の標準的な3次治療であるTrifluridine-TipiracilやRegorafenibの結果と比べても良好であった9,10)。
KRASG12C阻害に対する反応としてEGFR経路が再活性化されるとされており、KRASG12C阻害薬と抗EGFR抗体薬の併用がより有効であると考えられている11)。KRASG12C変異陽性大腸癌に対してのSotorasibと抗EGFR抗体薬であるPanitumumabの併用療法における第I相試験でも奏効割合30%と報告され、Sotorasib単剤での奏効割合10%と比較し良好な結果となっている12)。
本試験においても、AdagrasibとCetuximabの併用療法群で最良治療効果が病勢進行(PD: progressive disease)であった患者はおらず、併用療法での病勢制御割合の高さは患者のQOLの向上につながると考えられる。また、併用療法においても有害事象の相乗効果はなく、それぞれ単独治療の有害事象で報告されたものと同等であった。探索的なctDNAの解析結果からも、併用療法がより有効であると示唆されていた。
今回、Adagrasibによる治療の反応性とTP53およびPIK3CAの変異の有無には関連性がなく、大腸癌のKRASG12C阻害薬に対する耐性獲得のメカニズムにはMAPKシグナルの再活性化の関与が示唆された13)。しかしサンプルサイズが小さく、解釈には限界があるため、今後もこれらのメカニズムを解析する研究が望まれる。
本試験の限界としては、非無作為化試験であり群間の直接比較はできなかったことである。実際に後治療を受けた割合が単剤療法群において、併用療法群よりも多くなっていた。また登録症例数は少なく、大腸癌に対する標準治療が一通り行われた集団であり、予後不良な集団となっていた。
現在、KRASG12C陽性大腸癌の2次治療においてAdagrasibとCetuximabの併用療法と通常の化学療法を比較した第III相試験が行われており7)、本試験の第II相コホートとともに結果が待たれる。
まとめ複数の治療歴があるKRASG12C変異陽性の転移性大腸癌患者において、Adagrasibは単剤療法とCetuximab併用療法ともに良好な抗腫瘍効果を示した。併用療法群では奏効期間中央値が6ヵ月を超え、より有効であると考えられた。いずれの群でも有害事象は可逆的であり、忍容性が保たれていた。
日本語要約原稿作成:国立がん研究センター中央病院 消化管内科 小倉 望
監訳者コメント:
大腸癌におけるKRASG12C阻害薬は抗EGFR抗体薬との併用でより有望な結果を示した
KRAS変異に対する薬はundruggableと考えられてきていたが、KRASG12C阻害薬の出現により開発に注目が集まった。非小細胞肺癌においてSotorasibは奏効割合28%、病勢制御割合83%、またAdagrasibも奏効割合43%、奏効期間8.5ヵ月と良好な結果を示し、ともにFDA承認を得た。しかし大腸癌においてはSotorasib単剤では奏効割合が9.8%にとどまり、肺癌と比較し限られた結果であった。この乖離はKRASG12Cの細胞株を用いた研究で、KRASG12C阻害によりERKが一過性に阻害され、その後ERK経路のリバウンドが生じる可能性が報告されている14)。そして非小細胞肺癌と比較して、大腸癌においてはベースの受容体型チロシンキナーゼ(RTK)活性が高く、成長因子刺激に対する応答性が高いため、より高いレベルのERK経路活性が誘導されるとしている。このため大腸癌においては抗EGFR抗体との併用が有効である可能性が示唆されていた。本試験においてもAdagrasib単剤においては奏効割合が19%にとどまっていたが、Cetuximabとの併用により46%まで増強していたことから、抗EGFR抗体との併用が有望視される結果であった。本試験を踏まえ、第III相試験が進行中であり結果が期待されるが、いくつかの課題もある。
一つ目はKRASG12C阻害薬との最適な併用薬は何かという問題である。Ryanらは、KRASG12C阻害後に複数のRTKが野生型RAS(NRASおよびHRASを含む)のフィードバック再活性化を促進することを示し、この適応抵抗性を克服するためにSHP2やMEKの共同阻害が有効である可能性を示している15)。またRASを活性化させるグアニンヌクレオチド交換因子であるSOS1阻害の併用も抗腫瘍効果の増強が見込める可能性があるとしている。こうした報告からKRASG12C阻害薬とSHP2阻害薬もしくはSOS阻害薬/MEK阻害薬との併用の試験が進行中である。またKRASG12C大腸癌患者の4分の1以上がPI3K/mTOR経路の活性化変化を有し、また約8%の患者においてERK経路における他の共変化(BRAF、RAF1、HRAS、NRAS、MAP2K1、PTPN11、KRASなど)を有していたと報告されている14)。本研究においてはPIK3CA変異の状態と奏効との間に関連は認められなかったが、サンプルサイズが小さく、解析に限界があった可能性があり、こうした抵抗性メカニズムの解明も今後の開発とともに切望される。さらにKRASG12C阻害薬での治療が細胞周期の遺伝子への付随依存となっていることも明らかになっている5)。このためSotorasibとEverolimus(mTOR阻害薬)、SotorasibとPalbociclib(CDK4/6阻害薬)、AdagrasibとPalbociclibの組み合わせも、現在、進行固形癌において試験が進行中である。これだけ複数の併用療法による試験が行われており、大腸癌におけるKRASG12C阻害薬との最適な併用薬に対する検討は今後の課題である。
二つ目はKRASG12C阻害薬として、SotorasibやAdagrasibのほかに、GDC-6036(Divarasib)、JDQ443(Opnurasib)、JAB-21822(Glecirasib)、LY3537982と複数の薬剤が開発中である。これらはSotorasibより選択性が高く、より強力な抗腫瘍効果が見込める可能性を示唆しており、今後はこれらの使い分けが問題となる可能性もある。
まだ開発途中であり、不明瞭な点も多いがKRASG12C阻害薬は大腸癌においても重要な薬剤となる可能性が高く、今後も開発に注目が必要である。
- 1) Nassar AH, et al.: N Engl J Med. 384(2): 185-187, 2021 [PubMed]
- 2) Salem M, et al.: Ann Oncol. 32(suppl 3): S218, 2021
- 3) Schirripa M, et al.: Clin Colorectal Cancer. 19(3): 219-225, 2020 [PubMed]
- 4) Henry JT, et al.: JCO Precis Oncol. 5: 613-621, 2021 [PubMed]
- 5) Hallin J, et al.: Cancer Discov. 10(1): 54-71, 2020 [PubMed]
- 6) Fell JB, et al.: J Med Chem. 63(13): 6679-6693, 2020 [PubMed]
- 7) Tabernero J, et al.: Ann Oncol. 32(suppl 3): S121, 2021
- 8) Tabernero J, et al.: J Clin Oncol. 39(4): 273-284, 2021 [PubMed]
- 9) Grothey A, et al.: Lancet. 381(9863): 303-312, 2013 [PubMed]
- 10) Mayer RJ, et al.: N Engl J Med. 372(20): 1909-1919, 2015 [PubMed]
- 11) Amodio V, et al.: Cancer Discov. 10(8): 1129-1139, 2020 [PubMed]
- 12) Kuboki Y, et al.: Ann Oncol. 33(suppl 7): S680-S681, 2022
- 13) Awad MM, et al.: N Engl J Med. 384(25): 2382-2393, 2021 [PubMed]
- 14) Akhave NS, et al.: Cancer Discov. 11(6): 1345-1352, 2021 [PubMed]
- 15) Ryan MB, et al.: Cell Rep. 39(12): 110993, 2022 [PubMed]
監訳・コメント:国立がん研究センター中央病院 消化管内科 廣瀬 俊晴
GI cancer-net
消化器癌治療の広場