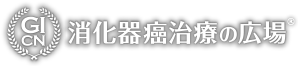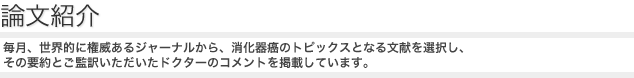9月
監修:聖マリアンナ医科大学 臨床腫瘍学講座 主任教授 砂川 優
胃癌
HER2陽性進行胃癌に対する二次治療としてのTrastuzumab DeruxtecanとRamucirumab+Paclitaxelの比較(DESTINY-Gastric04試験)
Kohei Shitara, et al.: N Engl J Med. 393(4): 336-348, 2025
【背景】
胃癌において、HER2陽性とは、免疫組織化学染色(IHC)3+、あるいはIHC2+かつin situ hybridization(ISH)陽性と定義され、胃癌全体の5~17%を占める1,2)。ToGA試験の結果に基づき、切除不能または転移性のHER2陽性胃癌(食道胃接合部腺癌を含む)の一次治療としては、抗HER2抗体Trastuzumab(Tmab)と化学療法の併用が標準である3-5)。さらに、KEYNOTE-811試験の結果を受け、PD-L1発現例(CPS 1以上)ではPembrolizumabを上乗せすることが標準治療となった6,7)。しかし、二次治療については、HER2陽性に特化した治療は存在せず、HER2 statusによらずRamucirumab+Paclitaxel療法が用いられてきた3,4,8)。
Trastuzumab Deruxtecan(T-DXd)は、抗HER2抗体にトポイソメラーゼI阻害薬の一種であるDeruxtecanをペイロードとして組み合わせた抗体薬物複合体である9,10)。日本と韓国で実施されたランダム化第II相試験DESTINY-Gastric01試験では、三次治療以降において標準治療と比較して、主要評価項目である奏効割合における優越性が認められるとともに生存期間延長効果も示され11)、米国および欧州で実施されたDESTINY-Gastric02試験や、中国でのDESTINY-Gastric06試験においても有効性が確認された12,13)。これらの結果を受け、複数の国でT-DXdがHER2陽性胃癌に対して承認されてきた。本試験DESTINY-Gastric04試験は、HER2陽性進行胃癌に対する二次治療として、T-DXdをRamucirumab+Paclitaxelと比較した検証的第III相試験である。
【対象と方法】
本試験の対象は、一次治療においてTmabを含む化学療法が施行された後に疾患進行が確認され、さらに、その後の再生検で中央判定によりHER2陽性が確認された症例である。主な適格基準は、ECOG PS 0または1、臓器機能が保たれていること、活動性の中枢神経系転移を認めないことなどであり、間質性肺疾患の既往を有する症例は除外された。T-DXd群(6.4mg/kg、3週毎)と、標準的なRamucirumab+Paclitaxel併用群に、1:1にランダム化割付がなされた。層別化因子は、直前の病理組織におけるHER2 status(IHC3+ vs. IHC2+かつISH陽性)、地域(中国を除くアジア vs. 西欧 vs. 中国およびその他)、一次治療中の病勢進行までの期間(6カ月未満 vs. 6カ月以上)とされた。主要評価項目は全生存期間であり、副次評価項目には無増悪生存期間、客観的奏効割合、病勢制御割合、奏効持続期間などが含まれた。統計設定としては、検出力を90%、全生存期間のハザード比(HR)を0.7(試験全体の両側α=5%)を見込み、予定症例登録数は490例と算出された。
【結果】
2021年5月から2024年10月にかけて、1,088例に対してHER2のスクリーニングが実施され、638例が陽性と判定されスクリーニングに進んだ。最終的に494例が登録され、T-DXd群246例、Ramucirumab+Paclitaxel群248例にランダム化割付された。患者背景は両群間で概ね偏りなく、年齢中央値はT-DXd群で63.2歳、Ramucirumab+Paclitaxel群で64.3歳であった。男性はそれぞれ76.0%、82.7%を占め、HER2 statusは、IHC3+がT-DXd群で84.1%、Ramucirumab+Paclitaxel群で83.9%であった。免疫チェックポイント阻害薬の治療歴を有する症例はT-DXd群で15.9%、Ramucirumab+Paclitaxel群で15.3%に認められた。
主要評価項目である全生存期間の解析では、追跡期間中央値がT-DXd群16.8カ月、Ramucirumab+Paclitaxel群14.4カ月で、全生存期間中央値はT-DXd群14.7カ月(95% CI: 12.1-16.6)であり、Ramucirumab+Paclitaxel群11.4カ月(95% CI: 9.9-15.5)に対して、HR=0.70(95% CI: 0.55-0.90、p=0.004)と有意な延長がみられた。6カ月生存割合は83.5% vs. 74.4%、12カ月生存割合は57.6% vs. 48.9%、24カ月生存割合は29.0% vs. 13.9%であった。サブグループ解析では、T-DXdはいずれのサブグループでも概ね一貫してT-DXdにおいて良好な傾向を示した。
無増悪生存期間もT-DXd群で有意な延長がみられ、中央値はT-DXd群6.7カ月(95% CI: 5.6-7.1)、Ramucirumab+Paclitaxel群5.6カ月(95% CI: 4.9-5.8)で、HR=0.74(95% CI: 0.59-0.92、p=0.007)であった。奏効割合はT-DXd群44.3%(95% CI: 37.8-50.9)、Ramucirumab+Paclitaxel群29.1%(95% CI: 23.4-35.3)であり、T-DXd群で有意に高く(p<0.001)、病勢制御割合はT-DXd群91.9%(95% CI: 87.7-95.1)、Ramucirumab+Paclitaxel群75.9%(95% CI: 70.0-81.2)であった。奏効持続期間の中央値は、それぞれ7.4カ月(95% CI: 5.7-10.1)と5.3カ月(95% CI: 4.1-5.7)であった。後治療は、T-DXd群の51.2%、Ramucirumab+Paclitaxel群の47.6%に実施された。Ramucirumab+Paclitaxel群では、25.8%の症例でT-DXdまたは中国で承認を受けているHER2を標的とした抗体薬物複合体のDisitamab Vedotinを投与されていた。
安全性の解析では、薬剤に関連した有害事象はT-DXd群の93.0%、Ramucirumab+Paclitaxel群の91.4%に認められ、grade 3以上の有害事象はそれぞれ50.0%と54.1%に認められた。主なgrade 3以上の有害事象として、好中球減少はT-DXd群28.7%、Ramucirumab+Paclitaxel群35.6%、貧血はそれぞれ13.9%、13.7%、白血球減少は7.4%、12.4%であった。T-DXdに特徴的な間質性肺疾患は、34例(13.9%)に発現し、そのうちgrade 1が7例(2.9%)、grade 2が26例(10.7%)、grade 3は1例(0.4%)であり、grade 4以上は認めなかった。一方で、Ramucirumab+Paclitaxel群でも3例(1.3%)に間質性肺疾患が発症し、grade 3が2例(0.9%)、grade 5が1例(0.4%)であった。
左室機能障害はT-DXd群で6例(2.5%)に発現し、grade 2が3例(1.2%)、grade 3が3例(1.2%)であり、Ramucirumab+Paclitaxel群では4例(1.7%)に生じ、grade 1が2例(0.9%)、grade 2が2例(0.9%)であった。治療関連死はT-DXd群で4例(1.6%)に発生し、上部消化管出血、腸閉塞、突然死、不明がそれぞれ1例であった。Ramucirumab+Paclitaxel群では2例(0.9%)に発生し、胃穿孔と間質性肺疾患が1例ずつであった。この結果により、安全性については両群の有害事象は概ね予測可能かつ管理可能なものであったと結論づけられている。治療中のQOLは両群とも大きな変化は認められなかった。
【考察と結論】
本試験のlimitationとしては、オープンラベル試験であったこと、サブグループ解析においては症例数が限られていたこと、HER2発現の腫瘍内不均一性が存在するため単一病変の再生検が全体のHER2 statusを完全には反映しない可能性があることなどが挙げられている。しかし、DESTINY-Gastric04試験は、Tmabを含む一次治療後のHER2陽性進行胃癌において、T-DXdが従来の標準治療であるRamucirumab+Paclitaxel療法と比較して生存期間を延長することを示した。既知の間質性肺疾患は生じたものの管理可能であり、この結果からT-DXdはHER2陽性進行胃癌に対する新たな二次治療の標準治療と位置付けられることが示された。
日本語要約原稿作成:近畿大学病院 腫瘍内科 原 颯一郎
監訳者コメント:
HER2陽性進行胃癌の二次治療において、T-DXdが標準治療のRamucirumab+Paclitaxel療法と比較して生存期間を延長した
本試験のポイントは、やはり治療前に再生検を実施し、HER2陽性が確認された症例のみに対象を絞り込んだ点である。本邦で実施されたWJOG7112G(T-ACT)試験では、Tmabを含む一次治療後において、PTX単独療法に対するPTX+Tmab併用療法の優越性は示されなかったが、その要因として、組織生検が実施された16例中、HER2陽性を維持していた症例は5例(31%)のみであったことが指摘されている14)。乳癌と異なり胃癌では、T-DXdはHER2低発現症例において効果が限定的であることが明らかとなっている15)。そのため、本試験において、症例の絞り込みがpositiveな結果につながった可能性が考えられる。
一方で、当然ながら一次治療後に生検可能病変を有する症例は、原発巣を有する症例などに限られる。T-DXdが適応拡大になった際の本邦の承認要件にもよるが、「生検が実施不可能な症例にどうすべきか?」「生検陰性であった症例にはRamucirumab+Paclitaxel療法後の三次治療でT-DXdを開始する前に生検を実施するのか?」「三次治療前の生検でもHER2陰性ならばT-DXdを使用しないのか?」といった新たなclinical questionが生じる。
また、HER2陽性胃癌に対するT-DXdの開発はさらに進んでおり、一次治療にフッ化ピリミジン系抗癌剤やPembrolizumabとの併用で、T-DXdを導入する2つの第III相試験DESTINY-Gastric05試験(NCT06731478)、ARTEMIDE-Gastric01試験(NCT06764875)が開始となっている。仮に、これらの試験の結果によって、一次治療でT-DXdが標準治療となれば、上記のclinical questionは結果的に解決することになる。さらなる治療開発の動向に注視すべきである。
- 1) Uzunparmak B, et al.: Ann Oncol. 34(11): 1035-1046, 2023 [PubMed]
- 2) Van Cutsem E, et al.: Gastric Cancer. 18(3): 476-484, 2015 [PubMed]
- 3) European Society for Medical Oncology: ESMO Living Guideline: Gastric Cancer v1.4 - September 2024 (https://www.esmo.org/living-guidelines/esmo-gastric-cancer-living-guideline)
- 4) Lordick F, et al.: Ann Oncol. 33(10): 1005-1020, 2022 [PubMed]
- 5) Shitara K, et al.: ESMO Open. 9(2): 102226, 2024 [PubMed]
- 6) Janjigian YY, et al.: Lancet. 402(10418): 2197-2208, 2023 [PubMed]
- 7) Janjigian YY, et al.: N Engl J Med. 391(14): 1360-1362, 2024 [PubMed]
- 8) Wilke H, et al.: Lancet Oncol. 15(11): 1224-1235, 2014 [PubMed]
- 9) Shitara K, et al.: Lancet Oncol. 20(6): 827-836, 2019 [PubMed]
- 10) Ogitani Y, et al.: Clin Cancer Res. 22(20): 5097-5108, 2016 [PubMed]
- 11) Shitara K, et al.: N Engl J Med. 382(25): 2419-2430, 2020 [PubMed]
- 12) Van Cutsem E, et al.: Lancet Oncol. 24(7): 744-756, 2023 [PubMed]
- 13) Shen L, et al.: Ann Oncol. 34(Suppl 4): S1542-S1543, 2023 [Ann Oncol]
- 14) Makiyama A, et al.: J Clin Oncol. 38(17): 1919-1927, 2020 [PubMed]
- 15) Yamaguchi K, et al.: J Clin Oncol. 41(4): 816-825, 2023 [PubMed]
監訳・コメント:近畿大学病院 腫瘍内科 三谷 誠一郎
GI cancer-net
消化器癌治療の広場