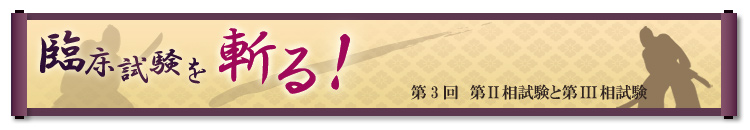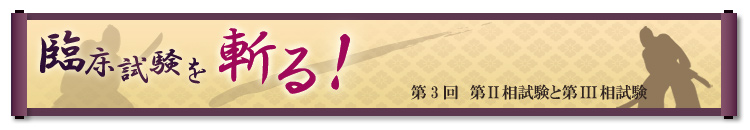今後の第II相試験の解釈
今後の第II相試験の解釈
坂本: 第III相試験が実臨床に大きな影響を与えることは言うまでもありませんが、最近では200〜300例を対象とした大規模な第II相試験の結果が影響を与えることもあります。今後、第II相試験をどう解釈していけばいいのでしょうか。
朴: ひと口に第II相試験といっても、新薬開発のための試験と、市販後の治療戦略を見極めるための試験とでは、目的もデザインも大きく異なります。OPUS試験が第II相試験でありながら実臨床に大きな影響を与えたのは、背景に1st-lineから3rd-lineまで抗EGFR抗体薬のデータが豊富にあったためです。全ての治療戦略を第III相試験で検証していくのは非現実的なので、臨床家に裁量を与える傍証の1つであるという解釈です。
一方で、未承認の新薬開発を目的とした第II相試験は実臨床に影響はありません。そもそも第III相試験で治療効果を示さない限り薬剤自体が承認されませんが、第II相試験はあくまで第III相試験に進める判断材料でしかないため、実臨床において影響を受けるようなことはあってはならないと思います。
森田: 第II相試験でもある程度の判断を行うことはできると思いますが、そのためには判断可能なサンプルサイズの設計が必要になります。ただ、特に医師主導で行われる無作為化第II相試験は、ある程度のsuggestionができるのではないかと感じています。
冒頭で申し上げた通り、これまでの臨床試験は第I相から第II相、第III相へと決められた形式で進められてきました。しかし、最近ではこの典型的な「相」を踏まえた進め方では対応しきれないケースも出始めています。主要評価項目も変化してきています。試験対象を大きな効果が期待されるサブ集団に絞れば、1群100例規模の第III相試験も実施可能かもしれません。乳癌の術前補助化学療法では、標準治療に対して5つの治療法をバイオマーカーによる複数のsubpopulationで比較・検討する800例規模の無作為化第II相試験、I-SPY2試験が行われています11)。今後は、このような戦略的な試験が増えていくのではないでしょうか。
朴: 第II相試験では、かつては薬効だけを見ればよかったのですが、今後は対象まで探索する必要があるため、無作為化試験が増えていくと思います。そして、これまでとは逆に、1,000例規模の無作為化第II相試験を行った後、200例で第III相試験を実施することもあり得ると思います。
坂本: 本日は臨床家と統計家という異なる立場からお話を伺いましたが、これからの臨床試験では今まで以上に臨床家と統計家とが情報交換をし、コンセンサスを得る努力も必要であると感じました。朴先生、森田先生、貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。