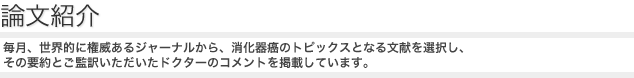7月
聖マリアンナ医科大学 臨床腫瘍学 准教授 砂川 優
胃癌 大腸癌
進行胃癌、大腸癌を対象としたRegorafenibとNivolumab併用療法の非盲検、用量漸増、用量拡大の第Ib相試験(EPOC1603)
Fukuoka S, et al.: J Clin Oncol. 38(18): 2053-2061, 2020
PD-1抗体などの免疫チェックポイント阻害薬は、胃癌を含めたさまざまな固形癌において予後の改善をもたらした1)。しかし、多くの症例で臨床的利益が得られないため、耐性克服のためのさらなる治療開発が重要である。大腸癌においては、ミスマッチ修復遺伝子の機能が保たれている症例(MSS、pMMR)ではPD-1抗体の有効性は認められなかった2)。PD-1抗体のその他の耐性機序として、制御性T細胞(Tregs)や腫瘍随伴マクロファージ(TAMs)などの免疫抑制細胞の関与が報告されている3,4)。
Regorafenibは血管新生ならびに癌増殖にかかわるキナーゼを標的とした阻害薬で、大腸癌のサルベージラインの標準治療薬のひとつであり5)、胃癌においても無作為化第II相試験の結果で有効性が示されている6)。Regorafenibは、コロニー刺激因子1受容体(CSF1R)の抑制下の腫瘍細胞モデルでTAMsを減少させる報告があり7)、胃癌患者においてVEGFR2阻害薬によりTAMsが減少したという報告がある8)。また、マウスモデルで、RegorafenibとPD-1抗体を併用し投与したほうが、それぞれ単剤で投与したよりも腫瘍の細胞増殖を抑制したという報告もあり7)、RegorafenibとNivolumabの併用療法の非盲検、用量漸増、用量拡大の第Ib相試験が計画された。
本試験の主要評価項目は、Nivolumab併用下でのRegorafenibの最大耐用量(MTD)と推奨用量を決定することであった。副次評価項目は、奏効率(ORR)、病勢制御割合(DCR)、無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)であった。探索的な評価項目は、アーカイブ腫瘍組織を用いたPD-L1染色(PD-L1 28-8抗体)によるCPS(Combined Positive Score)評価、TMB(Oncomine Tumor Mutation Load Assay)、MSIもしくはMMRステータス、HER2ならびにEBVステータス(胃癌)、RAS遺伝子解析(大腸癌)、腫瘍生検で得られた新鮮組織を用いた免疫表現型解析であった。
主たる適格規準は、組織学的に確認された進行ならびに転移性の固形癌、標準治療に不応もしくは不耐、ECOG PS 0-1、骨髄機能ならびに肝腎機能が保たれている等であった。また、PD-1もしくはPD-L1抗体を過去に受けている症例も適格とした。主たる除外基準は、Regorafenibの過去の投与歴、慢性的もしくは再燃性の自己免疫性疾患、重篤な合併症を有する等であった。
試験治療は1サイクルを28日間として、Regorafenib 80~160mg/日を21日内服した後に7日間休薬し、Nivolumabは3mg/kgを2週間ごとに点滴静注を行った。治療は病勢増悪もしくは不耐な有害事象が生じるまで行われた。用量制限毒性(DLT)は、7日以上継続するgrade 4の好中球減少、grade 4もしくは輸血を要するgrade 3の血小板減少、最大限の支持療法下におけるコントロール不能なgrade 3以上の非血液毒性、Nivolumabの中断やRegorafenibの設定用量の70%未満までに減量を要する有害事象であった。
試験デザインとして、用量漸増パートは古典的な3+3デザインで行われ、用量拡大パートでは約30症例の登録が予定された。用量拡大パートのサンプルサイズについては、事前設定した統計学的な仮説はなく、安全性と有効性を追加で評価する目的で行われた。有害事象はCTCAE v4.03に基づいて評価された。有効性の評価は、病勢増悪が認められるまで6週ごとにCTを施行し、RECIST v1.1に基づいて行われた。腫瘍生検は可能であれば、治療開始時と治療開始4~6週後に実施した。
2018年1月から2018年10月までに、胃癌25症例、大腸癌25症例の合計50症例が本試験に登録された。有効性と安全性データのカットオフは2019年4月23日で、PFSとOSのデータ更新は2019年9月1日に行った。他の固形癌も登録可能であったが、胃癌と大腸癌のみが登録された。患者背景として、ほとんどの症例がECOG PS 0(98%)、すべての患者で2レジメン以上の治療歴があり、96%の患者で血管新生阻害薬の治療歴があった。胃癌の7症例(28%)でPD-1もしくはPD-L1抗体の治療歴があったが、すべての症例において登録前までに病勢増悪が確認されていた。MSI-Hは大腸癌の1症例のみで、残りは全てがMSS/pMMRであった。胃癌では1症例でEBV陽性であり、大腸癌でRAS野生型は76%、RAS変異型が24%であった。治療サイクルの中央値は6サイクルで、データ更新時において16症例が治療継続中であった。試験治療の中止理由は、32症例が病勢増悪、1症例が治療関連の斑状丘疹状皮疹、1症例が糖尿病ケトアシドーシスによる治療関連死であった。
用量漸増パート(N=14)では、Regorafenib 160mg/日において、DLTが3症例で認められた(grade 3の斑状丘疹状皮疹、蛋白尿、大腸穿孔)。しかし、Regorafenibの80mg/日もしくは120mg/日ではDLTは認められなかった。以上から、Nivolumab併用下でのRegorafenibのMTDは120mg/日と決定した。しかし、用量拡大パート(N=36)において、grade 3の皮疹の頻度が高かったため、登録途中からRegorafenibの初期用量は80mg/日に減量した。初期用量が120mg/日であった25症例のうち、21症例(84%)で手掌足底発赤知覚不全症候群や斑状丘疹状皮疹が主たる原因で治療中の減量を要した。一方で、80mg/日が初期用量の症例では、2症例(9%)のみが治療中の減量を要した。有効性と安全性の評価から、Nivolumab併用下のRegorafenibの至適な推奨用量は80mg/日と考えられた。
全gradeの有害事象では、手掌足底発赤知覚不全症候群(70%)、高血圧(48%)、皮疹(42%)、疲労(40%)の頻度が高かった。Grade 3以上の有害事象では、皮疹(12%)、蛋白尿(12%)、手掌足底発赤知覚不全症候群(10%)の頻度が高かった。Grade 3以上の有害事象の割合は、Regorafenib 80mg/日と120mg/日で、それぞれ27%と44%であった。120mg/日の5症例(20%)でgrade 3の皮疹が認められた一方で、80mg/日の症例ではgrade 3以上の皮疹は認めなかった(grade 1-2:36%)。斑状丘疹状皮疹を認めた2症例では皮膚生検が行われ、PD-L1発現のある免疫細胞の浸潤が確認された。Grade 3の皮膚毒性が認められた全ての症例で、コルチコステロイドの投与により回復が認められた。重篤な有害事象は9症例(18%)で認められ、胃癌の1症例では、治療開始の約9ヵ月後において糖尿病ケトアシドーシスによる死亡を認めた。
ORRについては、全体で40%(95% CI: 26.4%-54.8%)、胃癌で44%(95% CI: 24.4%-65.1%)、大腸癌で36%(95% CI: 18.0%-57.5%)であった。MSI-Hを除いたMSS大腸癌におけるORRは33.3%であった。EBV陽性の胃癌症例(N=1)でCRを認めた。PD-1抗体もしくはPD-L1抗体の治療歴のある胃癌の7症例のうち3症例で奏効が認められた。大腸癌においては、肝転移よりも肺転移の症例のほうが、奏効割合が高かった(15.4% vs. 50.0%)。Regorafenib 80mg/日と120mg/日における奏効割合は、それぞれ45.5%と36.0%であった。DCRは86%(95% CI: 73.3%-94.2%)であり、ほとんどの症例で腫瘍縮小効果が認められた。
PFSの中央値は、胃癌で5.6ヵ月(95% CI: 2.7-10.4ヵ月)、大腸癌で7.9ヵ月(95% CI: 2.9ヵ月-未到達)であった。1年におけるPFS割合は、胃癌で22.4%、大腸癌で41.8%であった。OSの中央値は、胃癌で12.3ヵ月(95% CI: 5.3ヵ月-未到達)、大腸癌で未到達(95% CI: 9.8ヵ月-未到達)であった。データカットオフの時点で、全体で27症例が生存していた。1年のOS割合は、胃癌で55.3%、大腸癌で68.0%であった。
CPSによるPD-L1評価は48症例で行われ、TMB解析(カットオフ:上位4分の1)は47症例で行われた。PD-L1染色における奏効割合の評価では、胃癌ではCPS≧1群において60.0%、CPS<1群で35.7%であり、大腸癌ではCPS≧1群において25.0%、CPS<1群で43.8%であった。TMB解析における奏効割合の評価では、胃癌ではTMB高値群で50.0%、TMB低値群で44.4%であり、大腸癌ではTMB高値群において50.0%、TMB低値群で35.3%であった。PFS中央値に関しては、胃癌においてPD-L1 CPS≧1群において10.9ヵ月、CPS<1群で2.9ヵ月であり、TMB高値群で3.6ヵ月、TMB低値群で7.8ヵ月であった。大腸癌においては、PD-L1 CPS≧1群において6.0ヵ月、CPS<1群で未到達であり、TMB高値群で12.5ヵ月、TMB低値群で7.9ヵ月であった。
本試験では、Regorafenib 80mg/日とNivolumab 3mg/㎏の併用療法における管理可能な安全性プロファイルが示され、将来的に有望な有効性のデータが得られた。本試験は小規模な臨床試験であり、今後はさらなる大規模なコホートにおける検証が必要である。
日本語要約原稿作成:埼玉県立がんセンター 消化器内科 高橋 直樹
監訳者コメント:
MSS大腸癌に対する新たな治療選択肢となるか?
MSI-H大腸癌に対する免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の有用性が報告されるなか9)、MSS大腸癌に対する治療選択肢は未だ発展途上である。MSS大腸癌では、腫瘍組織へのT細胞の浸潤割合が少なく、T細胞免疫が活性化されていない、いわゆるimmune-excludedやimmune-coldな腫瘍環境になっており、免疫応答を賦活化するためにさまざまな検討がなされてきた。
基礎研究においては、VEGF阻害はPD-1を含む腫瘍免疫抑制分子の発現を低下させることで疲弊T細胞を回復させ、腫瘍浸潤T細胞を活性化し、腫瘍関連マクロファージを誘導させると考えられている。また、VEGF阻害は制御性T細胞や、骨髄由来免疫抑制細胞の働きを抑えることでT細胞動員による局所免疫効果を高めることも報告されている。他癌種、特に腎細胞癌においては、同様のコンセプトであるマルチキナーゼ阻害剤とICIの併用療法による有効性が示されており、既に臨床で使用されている。また、肝細胞癌ではAtezolizumab+Bevacizumab併用療法の有効性が示され10)、ICIの併用療法は殺細胞剤、抗CTLA-4阻害から、抗VEGF阻害作用を含んだ併用療法へ発展しつつある。
さて、本レジメンの今後の展望である。直近では、仏国でのRegorafenibとAvelumab併用療法11)、また、米国でのRegorafenibとNivolumab併用療法の早期試験結果12)が報告された。いずれも有効性および安全性について、本試験のデータよりも若干見劣りする印象であり、一筋縄ではいかない印象を抱く。バイオマーカー解析について、古典的な大腸癌の臨床病理学的・分子生物学的な背景因子のみならず、腫瘍免疫にかかわる因子も検討した上で、有効性の期待できるpopulationを絞り込むことが、第III相試験で勝利するために必要だろう。
- 1) Kang YK, et al.: Lancet. 390(10111): 2461-2471, 2017 [PubMed]
- 2) O’Neil BH, et al.: PLoS One. 12(12): e0189848, 2017 [PubMed] この論文は無料です
- 3) Togashi Y, et al.: Nat Rev Clin Oncol. 16(6): 356-371, 2019 [PubMed]
- 4) Mantovani A, et al.: Nat Rev Clin Oncol. 14(7): 399-416, 2017 [PubMed] この論文は無料です
- 5) Grothey A, et al.: Lancet. 381(9863): 303-312, 2013 [PubMed]
- 6) Pavlakis N, et al.: J Clin Oncol. 34(23): 2728-2735, 2016 [PubMed] この論文は無料です
- 7) Hoff S, et al.: Ann Oncol. 28(suppl_5): v403-v427, 2017 [OncologyPRO]
- 8) Tada Y, et al.: J Immunother Cancer. 6(1): 106, 2018 [PubMed] この論文は無料です
- 9) Le DT, et al.: J Clin Oncol. 38(1): 11-19, 2020 [PubMed] この論文は無料です
- 10) Finn RS, et al.: New Engl J Med. 382(20): 1894-1905, 2020 [PubMed]
- 11) Cousin S, et al.: J Clin Oncol. 38(suppl; abstr 4019), 2020
- 12) Kim R, et al.: Ann Oncol. 31(suppl 3; abstr O-20), 2020
監訳・コメント:埼玉県立がんセンター 消化器内科 原 浩樹
GI cancer-net
消化器癌治療の広場